孤独と衝動、幻想と優しさ——浅井健一の音楽には、言葉にできない感情の揺らぎが宿っている。
1990年、BLANKEY JET CITYの結成から始まったその旅は、SHERBETS、AJICO、JUDE、PONTIACS、そしてソロ名義へと枝分かれしながら、常に新しい表現を探し続けてきました。
ギターの音色、詩の語感、ライブの空気、絵画や詩集にまで広がる創作の世界——そのすべてが、浅井健一という表現者の「今」を形づくっています。
本記事では、彼のバンド遍歴と音楽活動を時系列で丁寧に辿りながら、ライブ演出、使用機材、歌詞の世界観、映画との関わり、SNSでのファンの反応までを包括的に整理。
浅井健一という存在が、なぜ今も多くの人の心を揺さぶり続けるのか。その理由を、音楽と表現の軌跡から紐解いていきます。
▶▶ 浅井健一さんのDVDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
▶▶ 浅井健一さんの曲をアマゾンミュージックでチェックしてみる
浅井健一の音楽活動とバンド遍歴を整理
BLANKEY JET CITYの結成と解散までの流れ

BLANKEY JET CITYは1990年に浅井健一、照井利幸、中村達也の3人によって結成された。浅井と照井は名古屋で「スキャッツ」というバンドで活動していたが、浅井が上京した後に中村と再会し、照井も合流する形でバンドが始動した。結成当初は中村がマネージャー的な立場だったが、3人でセッションを重ねるうちに手応えを感じ、正式にドラマーとして加入した。
1990年8月にはテレビ番組「イカすバンド天国」に出演し、5週連続で勝ち抜き、グランドキングの称号を獲得。これをきっかけに東芝EMIと契約し、1991年にロンドン録音のデビューアルバム『Red Guitar And The Truth』をリリースした。荒削りながらも鋭い感性が光る楽曲は、当時の若者たちの心を捉え、オリコンチャートでも好成績を収めた。
その後も『Bang!』『C.B.Jim』『SKUNK』などのアルバムを発表し、ライブ活動も精力的に行った。1994年には日本武道館での初ライブを成功させ、1995年にはイングランドでの海外ライブも実現している。音楽性の違いや個性の強さから、活動中も解散の話が出ることがあったが、代々木公園でのフリーライブ「Are You Happy?」が好評だったことで、一度は解散の流れが止まった。
しかし、1996年以降はメンバーそれぞれがソロプロジェクトを始動させ、バンドとしての活動は徐々に減少。浅井はSHERBETS、照井はJoe Brown、中村はLOSALIOSとしてそれぞれの道を歩み始めた。2000年には正式に解散を発表し、10年間の活動に幕を下ろした。解散後もその音楽は多くの人に聴かれ続け、現在も語り継がれている。
SHERBETSでの創作とレーベル設立
BLANKEY JET CITYの解散後、浅井健一は自身の音楽的探求を続けるためにSHERBETSを立ち上げました。メンバーには仲田憲市(ベース)、外村公敏(ドラム)、福士久美子(キーボード・コーラス)を迎え、浅井がボーカルとギターを担当しています。バンドは、サイケデリックで映画的な音像を軸に、幻想的で詩的な世界観を描く楽曲を多数発表してきました。
SHERBETSの活動は、浅井が設立した自主レーベル「SEXY STONES RECORDS」を通じて展開されています。このレーベルは、既存の枠にとらわれない自由な創作を可能にする場として機能しており、音楽だけでなくアートや詩集の出版など、多岐にわたる表現活動を支えています。
2025年には、SHERBETSとして2年ぶりとなる全国ツアー「BEST SELECTION TOUR」が開催されます。11月21日の岡山公演を皮切りに、福岡、長野、仙台、札幌、大阪、名古屋、東京の8都市を巡る予定です。このツアーでは、過去の代表曲から最新作までを網羅したセットリストが組まれ、SHERBETSならではの濃密な音楽空間が展開されます。
ライブでは、幻想的な照明演出と緻密な音響設計が融合し、観客を物語の中に引き込むような体験が生まれます。浅井の歌声とギターが描く情景は、現実と夢の境界を曖昧にしながら、聴く人それぞれの記憶や感情に静かに触れていきます。
SHERBETSの活動は、単なる音楽ユニットにとどまらず、浅井健一が築いてきた創作の軌跡そのものを体現しています。レーベルの運営からライブ演出、アート作品の発表まで、すべてがひとつの表現として連動しており、そこには一貫した美意識と探究心が息づいています。
AJICOでのUAとの共演と音楽性

AJICOは、浅井健一とUAが中心となって2000年に結成されたバンドです。メンバーには、ベースのTOKIE、ドラムの椎野恭一が加わり、4人編成で活動を開始しました。UAのアルバム制作をきっかけに浅井との音楽的な交流が深まり、自然な流れでバンドが誕生しています。
初期のAJICOは、ジャズやオルタナティブロックの要素を取り入れた独特の音楽性で注目を集めました。2000年の「RISING SUN ROCK FESTIVAL」で初登場し、同年にシングル「波動」でメジャーデビュー。翌2001年にはアルバム『深緑』をリリースし、全国ツアー「2001年AJICOの旅」を開催しました。活動期間は短かったものの、濃密な表現とライブパフォーマンスが印象深く、伝説的な存在として語られるようになりました。
2021年には20年ぶりに再始動し、新作EP『接続』を発表。ライブツアー「AJICO Tour 接続」も開催され、フェスやイベントへの出演も重ねました。再始動後の楽曲は、ファンキーさやジャズ感、ボサノバのリズムなどが織り交ぜられ、ジャンルを超えた自由な音楽が展開されています。
2024年にはEP『ラヴの元型』をリリースし、全国11ヵ所を巡るツアー「アジコの元型」を開催。東京・日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブも予定されており、AJICOとしては初の“音楽の聖地”での公演となります。メンバーそれぞれがソロ活動を並行して行っているため、AJICOの活動は断続的ではありますが、互いのタイミングが合えば自然と再び集まるというスタイルが続いています。
楽曲制作においては、浅井が膨大な数のフレーズをストックしており、そこから選び出して曲に仕上げる手法が取られています。録音は一発録りが基本で、ライブ感を重視したスタイルが貫かれています。歌詞は浅井とUAがそれぞれ担当し、社会的なメッセージや個人的な感情が織り込まれています。
AJICOは、ジャンルに縛られない音楽性と、メンバー間の信頼関係によって成り立っているバンドです。再始動後もその姿勢は変わらず、聴く人の心に静かに響く作品を届け続けています。
JUDE・PONTIACSなどのプロジェクト活動
浅井健一は、BLANKEY JET CITYの活動終了後も、音楽への探究を止めることなく、JUDEやPONTIACSといった複数のプロジェクトを立ち上げています。それぞれのバンドは異なる音楽的アプローチを持ち、浅井の創作の幅広さを感じさせる活動となっています。
JUDEは、2002年頃から始動したプロジェクトで、浅井がボーカルとギターを担当し、メンバーには福士久美子(キーボード)、仲田憲市(ベース)、外村公敏(ドラム)などが参加しています。SHERBETSと重なるメンバー構成ながら、JUDEではよりストレートなロックサウンドが展開されており、荒々しさと洗練が同居する楽曲が特徴です。ライブでは、浅井のギターが前面に出たエネルギッシュな演奏が印象的で、観客との距離感も近く、熱量の高い空間が生まれています。
一方、PONTIACSは2010年に結成されたバンドで、浅井健一(Vo/G)、照井利幸(Ba)、有松益男(Dr)という編成でスタートしました。照井はBLANKEY JET CITY時代の盟友であり、再びタッグを組んだことで話題を集めました。PONTIACSでは、ブルースやガレージロックの要素を取り入れた重厚なサウンドが展開されており、1stアルバム『GALAXY HEAD MEETING』はその世界観を色濃く反映しています。
PONTIACSは結成初年度から精力的にライブ活動を行い、FUJI ROCK FESTIVALやARABAKI ROCK FEST.などの大型フェスにも出演しました。2011年には照井が脱退し、以降は有松との2人体制で活動が続けられましたが、現在はプロジェクトとしての動きは落ち着いています。
これらのプロジェクトは、浅井健一が音楽を通じて異なる表現を試みる場として機能しており、ジャンルやスタイルに縛られない自由な創作が貫かれています。バンドごとに異なるメンバー構成も、音楽の質感や方向性に影響を与えており、浅井の音楽世界をより立体的に感じることができます。
ソロ名義でのリリースとライブ展開
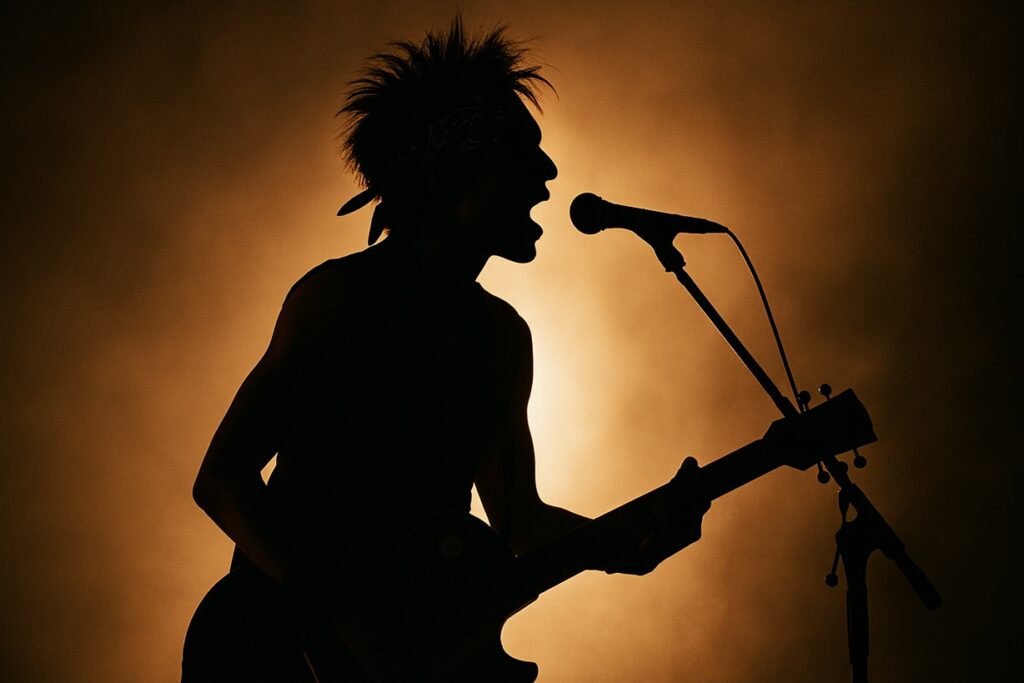
浅井健一は2006年にソロ名義での活動を本格的に開始し、同年9月にアルバム『Johnny Hell』を発表しました。これまでのバンド活動とは異なり、より個人的な視点や感情が反映された作品となっており、荒々しさと繊細さが同居する独自の音楽世界が展開されています。
その後もソロ名義でのリリースは続き、2017年には『METEO』を発表。この作品では、浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLSという新たなプロジェクト名義での制作が行われ、バンドサウンドとソロ表現の融合が試みられました。ギターの響きやリズムの構成においても、これまでの作品とは異なるアプローチが見られ、浅井の音楽的探究が感じられる内容となっています。
2021年には約1年半ぶりとなるソロアルバム『Caramel Guerrilla』をリリース。このアルバムでは、少女や都市の風景、心の揺らぎなどをテーマにした楽曲が並び、浅井らしい言葉選びと音の構築が際立っています。収録曲「ラッコの逆襲」や「水色のちょうちょ」などは、ユーモアと幻想が交錯する世界観を持ち、聴く人の想像力を刺激します。
ライブ活動においては、バンド編成と弾き語りの両方を使い分けながら、観客との距離感を大切にしたステージが展開されています。2024年にはアルバム『OVER HEAD POP』を発表し、それに伴う全国ツアー「OVER HEAD POP TOUR」を開催。ツアー最終公演の模様はライブフィルムとして記録され、2025年には東京・シネマート新宿で一夜限りの上映会が行われました。
ライブでは、浅井のギターと歌が空間を包み込み、観客の感情に静かに寄り添うような演奏が印象的です。セットリストには新旧の楽曲が織り交ぜられ、浅井の音楽の軌跡を辿るような構成が組まれています。ソロ名義での活動は、浅井健一が自身の内面と向き合いながら、音楽を通じて語りかける場となっています。
映画との関わりと劇中歌提供
浅井健一は音楽活動にとどまらず、映画の世界にも積極的に関与しています。出演や劇中歌の提供を通じて、映像と音楽の融合を試みており、その存在感はスクリーンの中でも際立っています。
代表的な出演作としては、2013年公開の映画『VANISHING POINT』があります。この作品は、BLANKEY JET CITYの元メンバーである照井利幸、中村達也とともに出演しており、音楽と映像が一体となったライブドキュメンタリーとして制作されました。浅井の演奏シーンやインタビューが収められ、彼の音楽に対する姿勢や人間性が垣間見える内容となっています。
また、アニメーション作品『Highway Jenny』にも出演しており、短編ながらも独特の世界観が展開される中で、浅井の音楽が物語の雰囲気を支えています。映像作品においても、彼の音楽は単なるBGMではなく、登場人物の感情や場面の空気を繊細に補完する役割を果たしています。
劇中歌の提供としては、2009年公開の映画『クローズZEROⅡ』に楽曲「SPRING SNOW」を提供しています。この曲は、物語の緊張感や登場人物の内面を彩る重要な要素として使用され、映画の印象を深める一因となりました。配信限定でリリースされたこの楽曲は、映画ファンだけでなく音楽ファンからも支持を集めています。
浅井健一の映画への関わりは、単なる出演や楽曲提供にとどまらず、作品全体の空気を形づくる一部として機能しています。音楽と映像の境界を越えた表現は、彼の創作活動の幅広さを示すものであり、今後もそのような試みが続いていくことが期待されています。
フェス出演歴とライブ会場の傾向

浅井健一は、BLANKEY JET CITY時代から現在に至るまで、国内外の音楽フェスティバルに数多く出演してきました。代表的なフェスには、FUJI ROCK FESTIVAL、RISING SUN ROCK FESTIVAL、COUNTDOWN JAPAN、VIVA LA ROCKなどがあり、いずれもロックファンの熱気に包まれる場で存在感を示しています。フェスでは、バンド編成での出演が多く、エネルギッシュな演奏と観客との呼応が印象的です。
ライブ会場の選定においては、ライブハウスからホール、野外ステージまで幅広く対応しており、都市部だけでなく地方都市にも積極的に足を運んでいます。2025年の「BEST SELECTION TOUR」では、仙台darwin、BIGCAT(大阪)、Zepp Shinjuku(東京)などのライブハウスを中心に、観客との距離が近い空間での演奏が行われました。このツアーでは、浅井健一の全キャリアから選ばれた楽曲が披露され、BLANKEY JET CITY、JUDE、SHERBETS、AJICO、ソロ名義の曲がバランスよく組み込まれています。
セットリストには、代表曲だけでなく、普段あまり演奏されないレアな楽曲も含まれており、長年のファンにとっても新鮮な体験となっています。ライブでは、浅井のギターとボーカルが空間を支配し、ドラムやベースとの一体感が高まり、観客の感情を揺さぶるような瞬間が生まれます。演奏の合間にはユーモアを交えたMCもあり、ステージ上の浅井健一は音楽だけでなく人間味でも魅力を放っています。
ライブの演出はシンプルながらも緻密で、照明や音響の使い方にこだわりが感じられます。観客との距離感を大切にしながら、空間全体を包み込むような演奏が展開され、ライブ終了後には「生きていてよかった」と感じるような余韻が残ることもあります。浅井健一のライブは、音楽を聴くだけでなく、心で感じる体験として記憶に残るものとなっています。
▶▶ 浅井健一さんのDVDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
▶▶ 浅井健一さんの曲をアマゾンミュージックでチェックしてみる
浅井健一の表現手法と音楽以外の活動
歌詞に込められた語感と世界観

浅井健一の歌詞は、現実の断片と幻想的な情景が交錯する独特の世界観を持っています。都市の片隅や廃墟、夜のショーウィンドウなど、日常の中に潜む非日常を切り取るような描写が多く、聴く人の記憶や感情に静かに触れてきます。そこには、少年期の衝動や孤独、社会への違和感といったテーマが織り込まれており、浅井の視点がそのまま言葉になっているような感覚を覚えます。
彼の詩には、比喩や造語が頻繁に登場します。例えば「戦闘服を着た大男がミルクシェイクを撒き散らす」といった表現は、現実ではあり得ない光景でありながら、感情の混乱や社会の歪みを象徴するものとして機能しています。こうした言葉の選び方は、意味よりも響きやリズムを重視しており、音楽と一体となった詩的な構造を生み出しています。
また、浅井の歌詞には暴力的で刹那的な不良たちが登場することが多く、彼らは単なる反社会的存在ではなく、純粋さや孤独を抱えた象徴として描かれています。「腐ったやつを正しいやつが引き裂いてやる」「神様、あなたは純粋な心を持っていますか」といったフレーズには、社会への疑問と個人の葛藤が込められており、聴く者に強い印象を残します。
一方で、浅井の歌詞には優しさや希望も感じられます。「雨が全部ジュースだったら」「小瓶に詰めた青いチョコ」など、柔らかくてユーモラスな表現が、現実の厳しさの中にある小さな救いを示しています。こうした言葉は、聴く人の心に余韻を残し、日常の中にある美しさや可能性をそっと照らしてくれます。
浅井健一の歌詞は、音楽と密接に結びついた語感の世界であり、聴く人の感覚に直接語りかける力を持っています。意味を超えた響きの中に、彼自身の人生観や社会への視点が込められており、その詩世界は今も多くの人に影響を与え続けています。
影響を受けた海外アーティスト
浅井健一の音楽には、アメリカやイギリスを中心とした海外アーティストの影響が随所に感じられます。特にロック、パンク、ブルース、レゲエといったジャンルからの刺激が強く、彼のギターフレーズや歌唱スタイル、さらにはステージングにまでその影響が色濃く表れています。
最初に衝撃を受けたのはThe Rolling Stonesで、ミック・ジャガーの存在感やキース・リチャーズのギターの鳴らし方に強く惹かれたとされています。浅井のギターには、ストーンズのようなラフでグルーヴィーな感触が宿っており、音の隙間や余韻の使い方にも共通点が見られます。
The Clashからは、音楽に社会性を持ち込む姿勢や、ジャンルを横断する自由な発想を学んでいます。浅井の歌詞には、社会への疑問や個人の葛藤が込められており、音楽を通じて何かを伝えようとする姿勢がThe Clashの精神と重なります。また、ライブでのエネルギーの放ち方や、観客との距離感の取り方にも影響が感じられます。
Bob Marleyの音楽からは、レゲエのリズム感や精神性を取り入れています。BLANKEY JET CITY後期やソロ作品には、ゆったりとしたビートや浮遊感のあるメロディが登場し、そこにはマーレーの音楽に通じる「魂の揺らぎ」が感じられます。浅井の歌声が持つ柔らかさと力強さの両面は、こうしたレゲエの影響によって育まれたものでもあります。
これらの海外アーティストから受けた影響は、単なる模倣ではなく、浅井健一自身のフィルターを通して再構築されています。彼の音楽は、ルーツを大切にしながらも、常に新しい表現を模索する姿勢によって成り立っており、聴く人にとっても発見のある作品となっています。
絵画・詩集・絵本などの創作活動

浅井健一は音楽活動と並行して、絵画や詩集、絵本などの創作にも力を注いでいます。彼の表現は音楽にとどまらず、視覚や言葉の世界にも広がっており、それぞれの分野で独自の感性が息づいています。
2025年には、東京・渋谷のギャラリー「GALLERY X BY PARCO」にて個展「Candy Store」が開催されました。この展示では、浅井が描いた新作の絵画や詩集、絵本などが公開され、来場者は彼の多面的な創作世界に触れることができました。展示空間には、キャンバスに描かれた鮮やかな色彩の作品が並び、抽象的でありながらもどこか懐かしさを感じさせる構図が印象的でした。
絵画作品には、動物や人物、風景などが登場しますが、写実的な描写よりも感情や記憶を象徴するような形で表現されています。色使いは大胆で、赤や青、黄色などの原色が多用されており、視覚的なインパクトとともに、浅井の内面がにじみ出るような雰囲気を醸し出しています。
詩集では、音楽の歌詞とは異なる文体で、より静かで内省的な言葉が綴られています。短いフレーズの中に、孤独や希望、日常のひとコマが凝縮されており、読む人の心にそっと語りかけるような余韻があります。絵本では、ユーモラスで少し不思議なキャラクターが登場し、子どもだけでなく大人にも響く物語が展開されています。
これらの創作活動は、浅井健一が音楽以外の手法でも自分自身を表現し続けている証であり、彼の世界観をより立体的に感じることができます。絵や言葉を通じて、音楽とは異なる角度から感情や思想を伝える姿勢は、彼の表現者としての深さを物語っています。
使用ギター・機材と音の質感
浅井健一の音作りには、ギターやアンプ、エフェクターといった機材選びが深く関わっています。彼のサウンドは、単なる機材の組み合わせではなく、それらをどう鳴らすかという姿勢に支えられています。
代表的なギターは、Gretsch PX6119 Chet Atkins Tennesseanで、BLANKEY JET CITY時代の象徴的な一本です。シングルコイルのハイロートロンピックアップを搭載し、木製ブリッジを接着固定するなど独自のカスタマイズが施されています。事故でネックを折ったこともあり、複数本を所有していたとされます。近年では、Gretschから公式にリリースされたKenichi Asai Signatureモデルも使用しており、本人のプレイスタイルに合わせた仕様が反映されています。
アンプはMarshall 1959 JMP Super Lead 100を軸に、Matchless DC-30やFender ’59 Bassman、VOX AC30などを曲や時期に応じて使い分けています。Marshallは改造された70年代製のPlexiを使用し、ボリュームを常に最大にしてナチュラルなオーバードライブを得ています。Matchlessは立体感のある音像を実現するために選ばれ、Fenderではブルースライクなトーンを追求しています。
エフェクターは最小限に抑えながらも、Pro Co RATやBOSS DM-2などを効果的に使用しています。特にDM-2は、浅井の音に広がりと奥行きを与える重要な役割を果たしており、ライブでも常にボードに組み込まれています。歪みや残響のニュアンスに細かくこだわり、音の倍音や空間の広がりを意識したセッティングが特徴です。
弦は太めのゲージ(.011-.048)を選び、爆音でアンプを鳴らし切ることで、浅井健一ならではの“ベンジーサウンド”が完成します。ライブとレコーディングでは機材の使い分けもあり、ステージ環境や楽曲の雰囲気に応じて柔軟に対応しています。
浅井健一の音作りは、機材の選定だけでなく、それをどう扱うかという感覚的な部分にまで踏み込んでいます。その探究心とこだわりが、唯一無二の音の質感を生み出しているのです。
SNSでのファン層と反応傾向

浅井健一の活動に対するファンの反応は、SNSを通じて日々共有されています。ライブの感想や新作への共感、アート作品への反響など、投稿内容は多岐にわたり、彼の表現に対する関心の高さがうかがえます。特にX(旧Twitter)やInstagramでは、ライブ当日の様子や展示会の感想がリアルタイムで発信されており、ファン同士の交流の場にもなっています。
ライブ関連の投稿では、「音が身体に染み込んだ」「MCが優しくて泣きそうになった」など、感情に寄り添う言葉が多く見られます。セットリストの構成や演奏の熱量に対する評価も高く、浅井の音楽が世代を超えて支持されていることが感じられます。若い世代のファンも増えており、親子でライブに訪れるケースも報告されています。
アート作品や詩集に対する反応も非常に活発で、個展「Candy Store」開催時には、展示された絵画や詩の一節を撮影した投稿が多数見られました。色彩や構図に対する感想だけでなく、「言葉が心に刺さった」「絵の中に物語が見えた」といったコメントが並び、音楽以外の表現にも深い共感が寄せられています。
また、浅井健一自身がSNSを通じて作品情報やライブ告知を発信しており、ファンとの距離感が近いことも特徴です。投稿には手描きのイラストや詩的な言葉が添えられることがあり、彼の創作姿勢や人柄が垣間見える内容となっています。こうした発信は、フォロワーにとって特別な贈り物のように受け取られており、コメント欄には感謝や応援の言葉が絶えません。
SNS上では、浅井健一の活動を通じて生まれる感情や記憶が共有され、ファン同士のつながりが育まれています。音楽、アート、言葉のすべてが彼の表現として受け止められ、そこに共鳴する人々の声が、日々静かに広がっています。
名言・MCに見る思想と姿勢
浅井健一のライブMCやインタビューには、彼の人生観や創作への姿勢が率直に表れています。音楽だけでなく、社会や人間関係に対する視点も独特で、時にユーモラスに、時に鋭く本質を突く言葉が印象に残ります。
「人生、美しく生きないと」という言葉には、浅井が大切にしている価値観が凝縮されています。うまく生きることよりも、自分のストーリーを美しく紡ぐことに重きを置いており、その姿勢は音楽やアートにも通じています。彼は「一生懸命に生きることが大事」とも語っており、仕事や表現を通じて誰かの役に立つことに喜びを見出しています。
ライブでは、観客との距離を縮めるような言葉が多く、時には「詩はカッコつけたらすぐ死ぬ」といった発言も飛び出します。これは、表現において本質を見失わないための戒めとも受け取れます。浅井の言葉には、飾らない率直さと、音楽的なリズムが感じられ、聴く人の心に自然と染み込んでいきます。
また、「俺は人間が奏でる音のほうが好き」と語るように、機械的な音よりも人の手による揺らぎや温度感を重視しています。これは、浅井が音楽を通じて人間らしさを伝えたいという思いの表れでもあります。彼の発言には、芸術作品に対する姿勢も垣間見え、「光がない作品は見たくない」と語る場面では、希望や救いのある表現を求める姿勢が明確に示されています。
浅井健一の言葉は、音楽の枠を超えて、生き方や価値観にまで響く力を持っています。その一言一言が、聴く人にとっての指針や励ましとなり、彼の表現世界をより深く理解する手がかりとなっています。
コラボアーティストとの関係性

浅井健一は、UAとのユニットAJICOをはじめ、数多くのアーティストとコラボレーションを重ねてきました。その関係性は、単なる音楽的な相性にとどまらず、創作に対する価値観や感性の共有に基づいて築かれています。互いの個性を尊重しながらも、融合によって新たな表現が生まれる場面が多く見られます。
AJICOでは、UAの柔らかく深みのある歌声と浅井の鋭く感情的なギターが交差し、ジャンルを超えた音楽が展開されました。再始動後も、互いの距離感を保ちながら自然体で制作を進めており、楽曲にはその空気感が反映されています。歌詞の分担や録音スタイルにも互いの信頼が感じられ、無理なく混ざり合う関係性が作品の魅力となっています。
他にも、照井利幸や中村達也といったBLANKEY JET CITY時代のメンバーとの再共演もあり、PONTIACSやVANISHING POINTなどのプロジェクトで再び音を重ねています。長年の付き合いだからこそ生まれる呼吸の合った演奏は、浅井の音楽に深みを与えています。
さらに、椎名林檎との対談やイベントでの共演など、ジャンルや世代を超えた交流も行われています。互いに影響を受け合いながら、音楽だけでなく思想や表現のあり方についても語り合う場面があり、浅井の創作活動に新たな視点をもたらしています。
コラボレーションにおいて浅井健一が大切にしているのは、相手の個性を引き出しながら、自分自身の表現も妥協せずに貫くことです。そのバランス感覚が、作品に自然な調和と緊張感をもたらし、聴く人にとっても新鮮な体験となっています。
浅井健一の創作活動を通して見える多面的な表現
- BLANKEY JET CITYは1990年に結成され2000年に解散した
- SHERBETSでは幻想的な音像と詩的な詞が展開されている
- AJICOはUAとの共演でジャンルを越えた音楽を生み出した
- JUDEではストレートなロックサウンドが中心となっている
- PONTIACSでは照井利幸との再共演が実現している
- ソロ名義では個人的な視点からの作品が多く発表されている
- ライブではバンド編成と弾き語りを使い分けている
- 映画作品では出演や劇中歌提供など多角的に関与している
- フェスではライブハウスから野外ステージまで幅広く出演
- 歌詞には比喩や造語が多く響きを重視した表現が多い
- 海外アーティストからの影響を独自に再構築している
- 絵画や詩集では音楽とは異なる視覚的表現を展開している
- ギターや機材選びに細かなこだわりが見られる
- SNSでは世代を超えたファン層からの反応が集まっている
- MCや発言には浅井健一の人生観や思想が反映されている
- コラボでは相手の個性を尊重しながら新たな表現を生んでいる
▶▶ 浅井健一さんのDVDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
▶▶ 浅井健一さんの曲をアマゾンミュージックでチェックしてみる
▶▶ よかったらこちらの記事もどうぞ



