真島昌利のことをもっと深く知りたいと思ったとき、どこから触れていいか迷うことがあります。ブルーハーツのギタリストとしての印象だけでなく、真島昌利が歩んできた人生や音楽に込めた思い、そして現在の活動までを知ることで、その魅力は何倍にも広がります。
言葉に宿る哲学、ギターに込めた感情、ファッションや趣味にまで滲む彼らしさ――それらすべてが真島昌利という人物を形づくっています。気づけば、彼の音楽が日々の風景に寄り添ってくれるようになります。
【この記事のポイント】
- 真島昌利の幼少期から現在までの人物像
- 真島昌利の作詞・作曲に込められた思想と表現力
- 真島昌利のギター演奏と使用機材の特徴
- 真島昌利のライブ活動とファンとの関係性
▶▶ 真島昌利さんのCDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
真島昌利のプロフィールと歩んだ道
幼少期と家族構成のエピソード
真島昌利は1962年2月20日、東京都日野市で生まれました。幼少期は池袋で過ごし、のちに花小金井へと引っ越しています。父親は電電公社(現在のNTT)に勤めており、家族は社宅で暮らしていました。兄が一人おり、2歳年上です。兄は音楽活動とは無縁でしたが、家にあったレコードが真島昌利の感性を育むきっかけとなりました。
性格は控えめで、物静かな少年だったとされています。人前に出るよりも、部屋で本を読んだりレコードを聴いたりする時間を好んでいたようです。音楽との出会いは中学1年生の頃、友人宅で聴いたビートルズの「ツイスト・アンド・シャウト」が衝撃となり、すぐにフォークギターを手に入れて練習を始めました。最初は教則本を使っていましたが、物足りなさを感じ、友人からコードを教わるようになります。
この頃から、音楽は彼にとって単なる趣味ではなく、心の拠り所となっていきました。孤独を感じることも多かった少年時代に、音楽は静かに寄り添う存在だったのです。家族との関係は穏やかで、特に父親の仕事の影響で転居があったことが、彼の感受性に影響を与えたとも考えられます。
学歴と進学にまつわる裏話
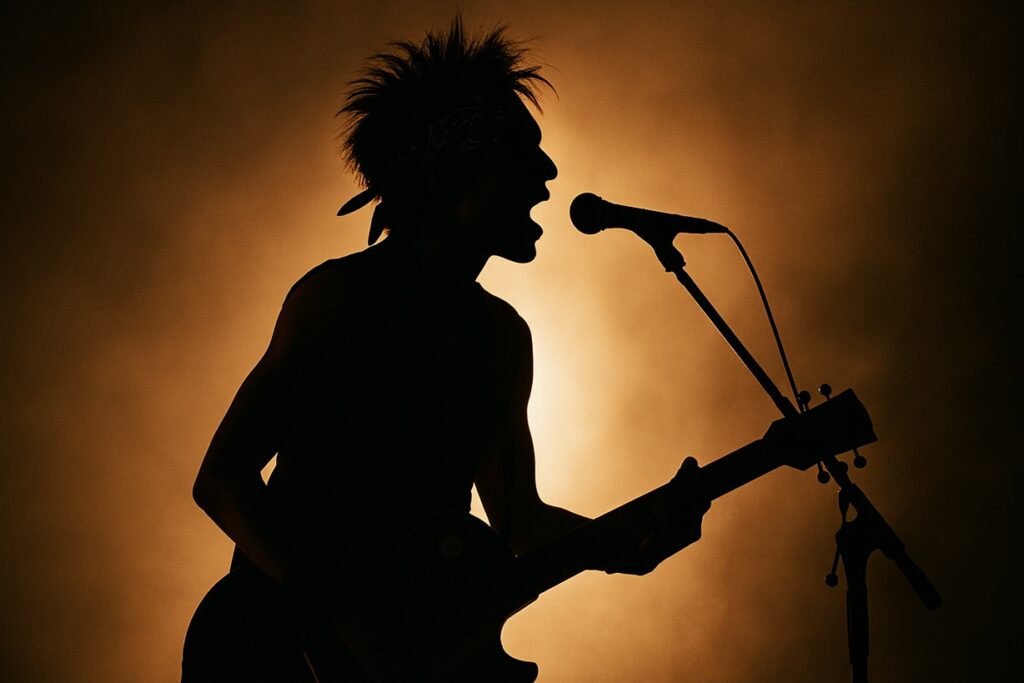
真島昌利は東京都立久留米西高等学校に通っていました。高校生活では、すでに音楽への情熱が強く、授業よりもギターに触れている時間の方が多かったとされています。実は、偏差値71の国学院久我山高校にも合格していましたが、男子校だったことや通学距離の理由から、より身近な久留米西高校を選んでいます。この選択には、合理的で現実的な彼の性格が表れているとも言えます。
高校時代はバンド活動に熱中し、卒業後すぐに本格的な音楽活動へと踏み出しました。大学には進学せず、ライブハウスを中心に活動を始めたことで、若いうちから実践的な経験を積むことができました。この頃に結成した「THE BREAKERS」は、東京のモッズシーンでも注目される存在となり、音楽事務所に所属して給料を得るほどの本格的な活動に発展しています。
進学よりも表現の場を選んだ姿勢は、後の作詞スタイルにもつながっています。真島昌利の歌詞には、教科書的な知識ではなく、現場で感じたことや日常の風景が生き生きと描かれています。文学的なセンスと現実感が共存するその表現力は、若い頃からの選択と経験に裏打ちされたものです。
ビートルズとの出会いがすべての始まり
真島昌利が音楽に目覚めたきっかけは、中学生の頃に友人の家で聴いたビートルズの「ツイスト・アンド・シャウト」でした。それまで音楽に特別な関心を持っていたわけではなく、戦闘機や野球などに夢中だった少年が、初めて「音楽って格好いい」と感じた瞬間だったとされています。その衝撃は大きく、すぐにギターを手に入れて、自分でも演奏してみたいという気持ちが芽生えました。
特にジョン・レノンの歌詞に強く惹かれたことが、真島昌利の音楽性に深く影響を与えています。彼が好んで聴いていたのは、ジョンが中心となって作った初期の楽曲で、ストレートな言葉と感情が込められた作品が多く含まれていました。その文学的な表現とロックの融合は、後に彼自身が作詞を手がける際の大きな指針となっています。
ビートルズとの出会いは、単なる音楽の入り口ではなく、表現者としての原点でもありました。ギターのコードを覚え、レコードを繰り返し聴きながら、自分の中にある感情や風景を音に乗せることを覚えていった過程は、彼の音楽人生の土台となっています。以降、彼の作品には英米ロックの影響が色濃く反映されており、ブルーハーツ時代の楽曲にもそのエッセンスが随所に見られます。
初めてのバンド活動とその解散

真島昌利が最初に本格的な音楽活動を始めたのは、高校時代に結成したバンド「THE BREAKERS」でした。このバンドは1978年にスタートし、東京のライブハウスを中心に活動していました。ジャンルはパンクロックを基盤にしながらも、モッズやロンドン・タイムズなどの影響を受けたスタイルで、原宿の歩行者天国でも演奏を行うなど、当時の若者文化の中で注目を集めていました。
メンバーは真島昌利を中心に、杉浦光治、篠原太郎、大槻敏彦らが在籍しており、時期によって編成が変わることもありました。真島は初期にはベースを担当していましたが、のちにギターへと転向しています。バンドは音楽事務所にも所属し、メジャーデビューの話も進んでいましたが、レコード会社との調整が難航し、デビューは白紙となりました。
その後、メンバー間の方向性の違いや脱退が続き、1985年1月のライブを最後に解散しています。この最後のステージには、後にブルーハーツをともに結成する甲本ヒロトが飛び入り参加しており、真島昌利の音楽人生において重要な転機となりました。
THE BREAKERSで演奏されていた楽曲の一部は、後のブルーハーツやソロ作品に受け継がれており、真島の音楽的な土台を築いた時期でもあります。バンドとしての活動は短命でしたが、彼の作詞・作曲のスタイルやライブパフォーマンスの原点がここにあります。
THE BREAKERSからブルーハーツへ
1985年、真島昌利は甲本ヒロトとともに「THE BLUE HEARTS」を結成しました。それまで活動していた「THE BREAKERS」が解散した直後のことで、音楽的な方向性を共有できる仲間との新たなスタートでした。バンド名は、誰にでも覚えやすく、意味を限定しない英語名を選んだ結果、「THE BLUE HEARTS」に決まっています。
真島昌利はギタリストとしてだけでなく、作詞・作曲の面でも中心的な役割を担いました。甲本ヒロトとほぼ半々の割合で楽曲制作を行い、それぞれの個性がバンドの音楽性に深みを与えています。真島の書く歌詞は、社会への疑問や個人の孤独をストレートに表現しながらも、どこか詩的で、聴く人の心に残る力を持っています。
1987年に「リンダリンダ」でメジャーデビューを果たすと、その勢いは一気に全国へと広がりました。この曲は甲本が作詞・作曲を担当していますが、真島が手がけた「終わらない歌」や「TRAIN-TRAIN」なども、同様に強いメッセージ性を持ち、若者たちの心を捉えました。彼らの楽曲は、単なるエンターテインメントではなく、時代の空気を映し出す鏡のような存在でした。
バンドは1995年に解散するまで、10年間にわたり精力的に活動を続けました。その間に発表された楽曲は、今もCMやドラマ、映画などで使用されており、世代を超えて支持されています。真島昌利の音楽は、ブルーハーツという枠を超えて、ロックの本質を問い続ける存在として、多くの人の記憶に刻まれています。
甲本ヒロトとの運命的な関係

真島昌利と甲本ヒロトの関係は、単なるバンドメンバーという枠を超えた、長年にわたる深い信頼と共鳴に支えられています。1985年に「THE BLUE HEARTS」を結成して以来、ふたりは「THE HIGH-LOWS」「ザ・クロマニヨンズ」と、40年近くにわたって同じバンドで活動を続けています。この継続性は、日本のロック史の中でも極めて稀な例です。
ふたりの音楽性は対照的です。甲本ヒロトはストレートで衝動的なパンクロックを好み、感情を爆発させるような表現が特徴です。一方、真島昌利は内省的で文学的な歌詞を得意とし、アコースティックな楽曲や比喩を多用するスタイルを持っています。この違いが、バンドの楽曲に奥行きを与え、幅広い層のファンに支持される理由にもなっています。
性格面でも、甲本が陽性で外向的なのに対し、真島は陰性で静かなタイプとされています。怒りの表現ひとつとっても、甲本は感情を表に出すのに対し、真島は黙ってその場を離れるようなタイプです。それでもふたりは、互いの違いを尊重し、補い合う関係を築いてきました。
音楽制作においても、作詞・作曲はほぼ半々で分担し、それぞれの世界観を持ち寄って作品を完成させています。歌詞に込める意味や哲学についても、ふたりは言葉を交わしながら、互いの考え方を理解しようとする姿勢を持ち続けています。そのやりとりは、まるで月を指す指を見つめ合うような、抽象的で詩的な対話にもなっています。
ファンの間では、ふたりの関係性は「運命共同体」とも呼ばれています。それは、単に長く一緒にいるからではなく、音楽に対する情熱や孤独感、そして表現への飽くなき探究心を共有しているからです。互いにとって、最も深く理解し合える存在でありながら、完全には交わらない「平行線のふたり」として、絶妙な距離感を保ち続けています。
ソロ活動と文学的な表現力の開花
真島昌利がソロ活動を始めたのは1989年、ブルーハーツの活動が一時的に休止していた時期でした。そのタイミングで制作された初のソロアルバム『夏のぬけがら』は、彼の音楽的な内面を丁寧に描き出した作品として知られています。バンドでは見せなかった繊細さや静けさが、アコースティックを基調としたサウンドに乗せて表現されており、聴く人の心に静かに染み込むような魅力があります。
このアルバムでは、真島昌利が少年時代に感じた風景や感情が、詩のような歌詞で綴られています。「夏が来て僕等」や「夕焼け多摩川」などの楽曲には、季節の移ろいや街の記憶が織り込まれており、まるで短編小説を読んでいるような感覚を覚えます。歌詞の中には、擬人化や比喩を巧みに使った表現が多く、文学的な感性が際立っています。
演奏面でも、コンピューターによる打ち込みを一切使わず、人の手による温かみのある音が全編を通して響いています。ピアノやアコースティックギター、ハーモニカなどが繊細に絡み合い、真島のしゃがれた声と絶妙に調和しています。特に「地球の一番はげた場所」では、軽快なレゲエアレンジの中に切なさが滲み、アルバム全体に深みを与えています。
『夏のぬけがら』は、ロックの激しさや反骨精神とは異なる、静かな情熱と哀愁を描いた作品です。その世界観は、音楽ファンだけでなく、詩や小説を愛する文芸ファンにも響くものとなり、ジャンルを超えて高い評価を受けています。真島昌利が持つ表現者としての幅広さと、言葉へのこだわりが、この作品を通して鮮やかに浮かび上がっています。
▶▶ 真島昌利さんのCDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
真島昌利の音楽性と現在の活動状況
ギター演奏スタイルと使用機材

真島昌利のギタープレイは、派手な技巧よりも、言葉や感情を支えるための演奏に重きを置いています。コードストロークは力強く、リズムに芯がありながらも、どこか温かみを感じさせるタッチが特徴です。音数を絞ったシンプルな構成でありながら、楽曲の世界観をしっかりと支える存在感があります。
使用するギターは、フェンダー・テレキャスターやギブソン・レスポールを中心に、時期や楽曲によって多彩です。ブルーハーツ時代には、TVイエローのギブソン・レスポール・スペシャルを愛用し、荒々しくも繊細なサウンドを生み出していました。ハイロウズ期には、レスポール・ジュニアやストラトキャスターも登場し、より多様な音色を探求しています。
クロマニヨンズ以降は、グレッチやマーチンのアコースティックギターも使用されており、ライブでは曲ごとにギターを持ち替える場面も見られます。特にGreco製のギターは、ブルーハーツ時代から長く使われており、本人のこだわりが感じられるポイントです。ギターにはステッカーが貼られていることも多く、個性と愛着がにじみ出ています。
アンプはMarshall JCM2000を使用し、セッティングはフルテンに近い状態で鳴らすことが多いようです。エフェクターは最小限に抑え、Maxon OD-808などで音量や歪みを調整する程度にとどめています。全体として、機材の選び方にも「余計なものはいらない」という哲学が貫かれており、音楽に対する姿勢がそのまま反映されています。
作詞・作曲に込められた哲学
真島昌利の作詞には、社会への違和感や個人の孤独、そして自由への強い希求が込められています。彼の言葉は、飾り気のない率直な表現でありながら、聴く人の心に深く残る力を持っています。例えば「終わらない歌」では、世界の理不尽さや抑圧に対する怒りを、直接的な言葉で突きつけながらも、歌い続けることの意味を問いかけています。その姿勢は、単なる反抗ではなく、声を上げることの尊さを伝えています。
真島の歌詞には、放送禁止用語を含むものもありますが、それは挑発ではなく、社会の矛盾や差別に対する真摯な抗議として使われています。「差別が僕を通り越して びしょぬれの心に突き刺さる」といった表現には、個人が受ける痛みや無理解を、詩的かつ生々しく描く力があります。彼の言葉は、誰かの代弁ではなく、自らの実感に根ざしたものとして響きます。
作曲面では、複雑な構成よりも、言葉のリズムや感情の流れを重視する傾向があります。「終わらない歌」などでは、基本的なコード進行を用いながら、メッセージそのものの強さを際立たせています。演奏技術に頼るのではなく、初期衝動のようなエネルギーをそのまま音に乗せることで、誰もが共感できる普遍性を生み出しています。
また、ソロ作品「アンダルシアに憧れて」では、物語性の強い歌詞とドラマティックな展開が印象的です。ギャングの一員として生きる主人公が、恋人との約束を果たせぬまま銃撃戦に巻き込まれていくという内容は、まるで映画のような構成で、真島の文学的な表現力が際立っています。彼の作品には、現実と幻想、怒りと優しさが同居しており、聴く人の心に長く残る余韻を与えます。
真島昌利の作詞・作曲は、時代やジャンルを超えて、音楽が持つ言葉の力を最大限に引き出すものです。その哲学は、ロックの枠を超えて、詩や文学の世界にも通じる深さを持っています。
ブルーハーツ時代の代表曲と世界観

真島昌利が作詞・作曲を手がけたブルーハーツ時代の楽曲には、社会への疑問や個人の葛藤、そして希望へのまなざしが込められています。代表曲「青空」は、抑圧された環境や不自由な生き方に対する静かな抵抗を描いた作品で、自由を求める心情がまっすぐに響きます。歌詞の中で「生まれたところや皮膚や目の色で いったいこの僕の何がわかるというのだろう」という一節は、差別や偏見に対する強いメッセージとして多くの人の心に残っています。
「人にやさしく」は、誰かに寄り添うことの大切さをシンプルな言葉で伝える楽曲です。「がんばれって言ってみるけど 本当はがんばってほしくない」というフレーズには、励ましの裏にある本音が込められており、聴く人の気持ちにそっと寄り添います。この曲は、応援歌としてだけでなく、優しさの本質を問いかける作品としても評価されています。
「チェインギャング」は、真島昌利の内面を色濃く反映した楽曲で、孤独や罪、そして生きることの苦しさが赤裸々に描かれています。仮面をつけて生きることへの息苦しさや、自分自身の弱さと向き合う姿勢が、ブルース調のメロディに乗せて表現されています。歌詞の中には「生きているっていうことは カッコ悪いかもしれない」という一節があり、真島の哲学的な視点が垣間見えます。
これらの楽曲は、単なるロックソングではなく、社会や人間の本質に迫る詩的な作品として位置づけられています。真島昌利の言葉は、時代を超えて共感を呼び続けており、ブルーハーツの音楽が今も多くの人に愛される理由のひとつとなっています。彼の世界観は、怒りや悲しみだけでなく、そこにある希望や優しさをも丁寧に描き出しており、聴く人の心に静かに残り続けます。
ハイロウズからクロマニヨンズへの流れ
1995年、THE BLUE HEARTSが解散した後、真島昌利は甲本ヒロトとともに「THE HIGH-LOWS」を結成しました。この新しいバンドでは、より自由な音楽表現を追求し、ブルーハーツ時代とは異なるアプローチでロックを展開しています。楽曲の幅も広がり、ポップな要素やユーモアを交えた作品が多く生まれました。代表曲「日曜日よりの使者」や「青春」などは、世代を超えて親しまれています。
THE HIGH-LOWSは、10年間にわたって活動を続け、2005年に活動休止を発表しました。その翌年、2006年には再び甲本ヒロトと真島昌利が中心となり、「ザ・クロマニヨンズ」を結成します。このバンドは、より原始的でストレートなロックンロールを志向しており、バンド名も旧石器時代のクロマニヨン人に由来しています。シンプルで力強い音楽を追求する姿勢が、バンドの核となっています。
ザ・クロマニヨンズでは、甲本と真島が作詞・作曲を分担し、ギターとボーカルの役割も柔軟にこなしています。楽曲は短く、勢いのあるものが多く、ライブではそのエネルギーが存分に発揮されています。観客との一体感を重視したパフォーマンスは、どの会場でも熱狂的な空気を生み出しています。
現在も精力的に活動を続けており、2024年には17枚目のアルバム『HEY! WONDER』をリリースし、全国43公演に及ぶツアーを開催しています。真島昌利は体調不良で一部公演を延期する場面もありましたが、すぐに復帰し、ファンとの約束を守る姿勢を貫いています。バンドとしての成熟と、変わらぬ情熱が、今も多くの人々を惹きつけています。
趣味が音楽に与えた影響

真島昌利は、音楽活動の傍らで読書や散歩を日常的に楽しんでいます。これらの趣味は、彼の歌詞や楽曲の世界観に深く影響を与えており、特に詩的な描写や風景の表現にその痕跡が見られます。読書に関しては、詩人・中原中也やビート・ジェネレーションの作家ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグなどから強い影響を受けており、文学的な感性が彼の言葉選びに反映されています。
ハイロウズ時代の楽曲「64,928-キャサディ・キャサディ」では、ケルアックの小説『路上』に登場する人物名がタイトルに使われており、旅や自由をテーマにした歌詞が展開されています。このように、読書によって得た思想やイメージが、彼の音楽に自然と溶け込んでいます。
散歩もまた、真島昌利にとって重要な創作の源です。ツアー先でも積極的に街を歩き、風景や空気を感じることでインスピレーションを得ています。スマートフォンを持たない彼は、散歩中に浮かんだメロディや歌詞を忘れないよう、急いで帰宅して録音することもあるそうです。こうした日常の中で生まれる感覚が、彼の楽曲にリアリティと温かみを与えています。
楽曲「散歩」や「今何歩?」など、散歩そのものをテーマにした作品も存在しており、歩くことが彼にとって単なる移動手段ではなく、心を整える時間であることがうかがえます。歌詞には、小金井公園や街角の風景など、具体的な場所が登場することもあり、聴く人にとっても身近な情景として響きます。
真島昌利の音楽は、こうした趣味によって育まれた感性が土台となっており、日常の中にある詩情を丁寧にすくい上げるスタイルが特徴です。文学と生活の両方を大切にする姿勢が、彼の作品に深みと親しみやすさを与えています。
ファッションとロックアイコンとしての存在感
真島昌利のファッションは、ロックンロールの精神を体現するスタイルとして、多くのファンに強い印象を残しています。黒の革ジャン、色落ちしたジーンズ、バンダナやブーツなど、彼の装いは一貫してシンプルで無骨ながら、芯の通った美学が感じられます。派手な装飾や流行に流されることなく、自分のスタイルを貫く姿勢が、ロックアイコンとしての存在感を際立たせています。
革ジャンは、ショット社製のライダースジャケットを中心に複数所有しており、ブルーハーツ時代から現在に至るまで着用されています。特にWライダース618は、現在もライブで着用されている定番アイテムです。これらのジャケットは、アメリカンロックの象徴とも言える存在で、真島昌利の音楽性とも深く結びついています。
バンダナも彼のトレードマークのひとつで、ブルーハーツ初期には白×えんじ色、90年代には黄色×赤、最近では白×赤など、時期によって異なる色柄を使い分けています。これらはインドやネパールの雑貨店で販売されている風呂敷サイズの布を折りたたんで使用しており、既製品ではない独自のこだわりが感じられます。
Tシャツにも個性が表れており、エルヴィス・プレスリーや中原中也、ジャック・ケルアックなど、彼が敬愛する人物の肖像がプリントされたものを好んで着用しています。これらはアートディレクター杉浦逸生が手がけたもので、ブルーハーツのジャケットデザインにも関わっていた人物です。真島昌利の思想や美意識が、衣服の選び方にも反映されています。
帽子やブーツなどの小物も、彼のスタイルを構成する重要な要素です。キャスケットやニット帽、インディアン風の羽根飾りなど、時期によって異なるアイテムを取り入れながらも、常に「自分らしさ」を失わない姿勢が貫かれています。ファッションを通じて、彼は音楽と同じように、自分の哲学や感情を表現しているのです。
真島昌利のファッションは、単なる衣装ではなく、彼の生き方そのものを映し出す鏡のような存在です。ステージ上でも日常でも、変わらぬスタイルを貫くことで、ファンにとっては安心感と憧れの象徴となっています。ロックアイコンとしての存在感は、こうした一貫性と誠実さによって築かれているのです。
現在のライブ活動とファンとの距離感

真島昌利は現在も「ザ・クロマニヨンズ」のギタリストとして、全国規模のライブツアーを精力的に行っています。2024年にはアルバム『HEY! WONDER』をリリースし、2月から6月にかけて全43公演のツアーを開催しました。体調不良による一部公演の延期もありましたが、すぐに復帰し、予定通りステージに立ち続ける姿勢は、音楽への誠実さとファンへの信頼を感じさせます。
ライブでは、真島昌利は多くを語らず、演奏と表情で思いを伝えるスタイルを貫いています。MCは最小限にとどめ、楽曲そのものがメッセージとなる構成が特徴です。その静かな佇まいと、ギターから放たれる力強い音が、観客との間に深い共鳴を生み出しています。言葉ではなく音で語る姿勢が、彼らしい距離感の取り方と言えます。
会場には、ブルーハーツ時代からのファンに加え、親子連れや若い世代の観客も多く見られます。世代を超えて支持される理由は、楽曲の普遍性と、ライブに込められた真摯なエネルギーにあります。ステージ上の真島昌利は、派手な演出を避け、あくまで音楽を中心に据えたパフォーマンスを展開しており、その姿勢が長年にわたってファンの信頼を集めています。
ライブのセットリストは、最新アルバムの楽曲に加え、過去の代表曲も織り交ぜられており、初めて観る人にも馴染みやすい構成となっています。演奏は一貫して生々しく、録音された音源とは異なるライブならではの熱量が感じられます。観客との一体感を重視したステージは、どの会場でも最後まで熱気に包まれ、音楽が人と人をつなぐ力を改めて実感させてくれます。
真島昌利のライブ活動は、単なる音楽イベントではなく、彼の生き方や哲学を体感できる場でもあります。ファンとの距離を保ちながらも、音楽を通じて深くつながるその姿勢は、時代を超えて愛される理由のひとつです。
真島昌利の音楽人生と魅力を総まとめ
- 真島昌利は東京都日野市出身で静かな少年時代を過ごした
- 高校は都立久留米西高校に進学し音楽活動を優先した
- ビートルズとの出会いが音楽への情熱を決定づけた
- 初のバンドTHE BREAKERSでライブ活動を経験した
- THE BLUE HEARTS結成で社会派ロックを確立した
- 甲本ヒロトとの関係は音楽的信頼に満ちている
- ソロ活動では文学的な歌詞表現が高く評価された
- ギター演奏はシンプルで感情を伝えるスタイルが特徴
- 使用機材はフェンダーやギブソンなどを長年愛用している
- 作詞では社会への疑問や孤独を率直に描いている
- ブルーハーツ時代の楽曲は今も世代を超えて支持されている
- ハイロウズからクロマニヨンズへと活動を継続している
- 読書や散歩などの趣味が歌詞の世界観に影響している
- ファッションは革ジャンやバンダナなど一貫したロックスタイル
- 現在もライブ活動を精力的に続けファンとの距離を大切にしている


