日本のロック史において、甲本ヒロトほど一貫して「音楽とは何か」を問い続け、鳴らし続けてきた人物は他にいないかもしれません。THE BLUE HEARTSでの衝撃的なデビューから、THE HIGH-LOWSでの挑戦、ザ・クロマニヨンズでの原点回帰、そしてブギ連での新たな表現まで——彼の音楽は常に時代の空気を切り裂き、聴く者の心に真っ直ぐ届いてきました。
本記事では、甲本ヒロトのバンド遍歴と音楽スタイルの変遷を軸に、彼の人物像や楽器へのこだわり、さらには病気や怪我を乗り越えてステージに立ち続ける姿勢までを網羅的に紹介します。岡山から東京へ、そして日本中へと響き渡ったその歌声とロックンロールの魂を、エピソードとともに紐解いていきましょう。
【この記事のポイント】
- 甲本ヒロトの音楽活動の流れとバンド遍歴
- 歌唱スタイルや楽器へのこだわりの詳細
- 家族や趣味など音楽以外の側面の紹介
- インタビューから見える価値観と人生観
▶▶ ザ・クロマニヨンズのCDなどをアマゾンでチェックしてみる
▶▶ 甲本ヒロトさんに関する本などをアマゾンでチェックしてみる
甲本ヒロトのバンド遍歴と音楽スタイル
初期バンド「ラウンド・アバウト」時代
甲本ヒロトが音楽の世界に足を踏み入れたのは、高校3年生の卒業間際のことです。剣道の授業中、友人から声をかけられたことがきっかけで、岡山で活動していたバンド「ラウンド・アバウト」にボーカルとして加入しました。もともとこのバンドは1980年頃に結成されており、甲本ヒロトが加わったことで新たな展開を迎えました。
バンド名は、ディープ・パープルの前身バンドに由来しており、洋楽への憧れが込められています。活動は岡山を拠点にしており、地元のラジオ番組に出演したり、長谷川楽器店でデモ音源を録音したりと、地域に根ざした形で展開されていました。1981年には山陽放送主催のコンテストに出場し、審査員特別賞を受賞するなど、一定の評価も得ています。
ライブ活動は限られており、1981年3月と8月に2回行われた記録があります。東京にも進出し、渋谷屋根裏でライブを行ったこともありました。その際には「らウンドアバウト なぞのXデー 8月15日」と書かれたフライヤーが配布され、岡山の「いつものとこ」である長谷川楽器店が拠点として記されていました。
演奏していた楽曲には、甲本ヒロト自身が作詞・作曲を手がけた「999」や「Jump’inJap 3-3-7」などがあり、後にザ・コーツやTHE BLUE HEARTSへと引き継がれる作品も含まれていました。演奏スタイルは、キンクスやローリング・ストーンズ、セックス・ピストルズのカバーも取り入れたロック色の強いもので、当時の若者らしいエネルギーが感じられます。
この時期の経験が、甲本ヒロトの音楽的な基盤を形作る重要な土台となりました。限られた活動ながらも、ライブや録音、コンテストへの参加を通じて、表現することの手応えを掴んでいった時期といえます。
THE BLUE HEARTS結成とその衝撃

甲本ヒロトと真島昌利が出会ったのは、1980年代初頭の東京モッズシーンでした。それぞれ「ザ・コーツ」「ザ・ブレイカーズ」というバンドで活動していた二人は、音楽的な価値観を共有し、1985年にTHE BLUE HEARTSを結成しました。バンド名は、誰にでも覚えやすく、音楽性を限定しないようにという意図で名付けられたものです。
メンバーは甲本ヒロト(ボーカル)、真島昌利(ギター)、河口純之助(ベース)、梶原徹也(ドラム)の4人で構成され、1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューを果たしました。この曲は、パンクロックの初期衝動をそのまま封じ込めたようなエネルギーに満ちており、「ドブネズミみたいに美しくなりたい」という歌詞が象徴するように、既存の価値観に対する強烈な反発と、純粋な願望が込められていました。
同年には1stアルバム『THE BLUE HEARTS』もリリースされ、「未来は僕等の手の中」「終わらない歌」「NO NO NO」など、ストレートなメッセージを持つ楽曲が並びました。これらの曲は、社会に対する違和感や若者の葛藤を真正面から歌い上げており、当時の閉塞感を打ち破るような力を持っていました。
THE BLUE HEARTSの音楽は、セックス・ピストルズやザ・クラッシュなどの海外パンクバンドの影響を受けつつも、日本語での表現にこだわり、誰にでも届く言葉で感情を伝えることを重視していました。その結果、ロックファンだけでなく、幅広い層に受け入れられ、テレビや映画、CMなどでも楽曲が使用されるようになりました。
バンドの活動は1995年まで続き、8枚のオリジナルアルバムを残して解散しましたが、その後も甲本ヒロトと真島昌利はTHE HIGH-LOWS、ザ・クロマニヨンズといった新たなバンドを結成し、音楽活動を継続しています。THE BLUE HEARTSの楽曲は、現在でも多くの人々に聴かれ続けており、日本のロック史において特別な位置を占めています。
▶▶ 詳しくはこちらの記事もどうぞ
THE HIGH-LOWSでの挑戦と変化
THE BLUE HEARTSの解散から間もない1995年、甲本ヒロトと真島昌利は新たなバンド「THE HIGH-LOWS」を結成しました。バンド名には上下の矢印が付けられ、音楽の振れ幅や自由な発想を象徴するような意味合いが込められています。メンバーには、調先人(ベース)、大島賢治(ドラム)、白井幹夫(キーボード)も加わり、5人編成でスタートしました。
デビューは同年10月、シングル「ミサイルマン」とアルバム『THE HIGH-LOWS』の同時リリースでした。この時期の楽曲には、ロックの衝動をそのまま閉じ込めたようなエネルギーがありながらも、メロディラインや歌詞の構成にはポップス的な工夫が見られました。THE BLUE HEARTS時代の荒々しさとは異なり、より滑らかで親しみやすい歌唱スタイルが採用されるようになりました。
1996年にはセックス・ピストルズの日本武道館公演でオープニング・アクトを務め、海外の伝説的バンドとの共演も果たしました。その後も「胸がドキドキ」「相談天国」などのシングルがヒットし、オリコンチャートでも上位にランクインするなど、幅広い層に支持されるようになりました。
1999年には、メンバー自身のスタジオで録音したアルバム『バームクーヘン』を発表。エンジニアを入れず、完全にセルフレコーディングで制作されたこの作品は、当時としては珍しい試みであり、音楽制作の自由度を追求する姿勢が表れています。収録曲「ハスキー(欲望という名の戦車)」はライブでも定番となり、バンドの代表曲のひとつとなりました。
2000年にはドラマ主題歌として起用された「青春」がヒットし、THE HIGH-LOWSの名前はさらに広く知られるようになりました。この頃の楽曲には、ロックの骨格を保ちながらも、より洗練されたアレンジや歌詞の深みが加わっており、バンドとしての成熟が感じられます。
2005年に活動休止を発表するまでの10年間で、THE HIGH-LOWSはシングル26作品、オリジナルアルバム8作品を発表し、ライブツアーも精力的に行いました。その音楽は、ロックとポップの境界を軽やかに越えながら、常に新しい表現を模索し続けたものでした。
▶▶ 詳しくはこちらの記事もどうぞ
ザ・クロマニヨンズでの現在の活動
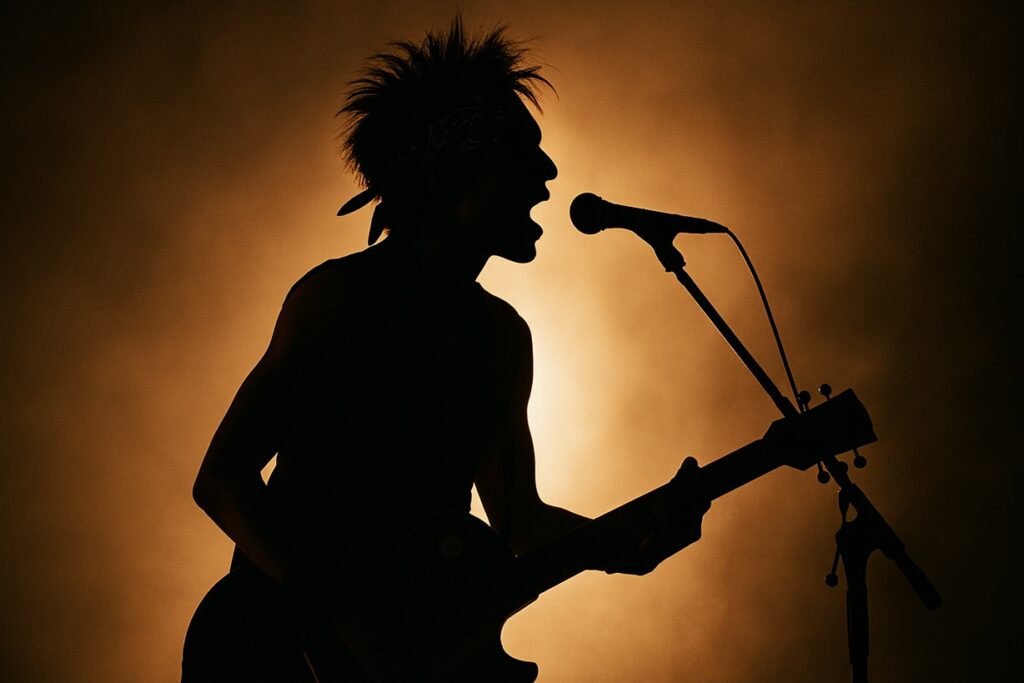
2006年、甲本ヒロトと真島昌利は新たなバンド「ザ・クロマニヨンズ」を結成しました。THE BLUE HEARTSやTHE HIGH-LOWSでの活動を経て、再び原点に立ち返るようなロックンロールを追求する姿勢がこのバンドには込められています。結成当初から、荒々しく力強い歌唱スタイルとシンプルなバンド編成で、ストレートなロックを鳴らし続けています。
デビューシングル「タリホー」は、疾走感あふれるサウンドと印象的なフレーズで注目を集めました。以降、毎年のようにアルバムを発表し、ライブツアーも精力的に行っています。2024年には17枚目のアルバム『HEY! WONDER』をリリースし、全国ツアーを展開しました。このアルバムでは、さらに高速なビートや多様なリズムが取り入れられ、バンドとしての挑戦が続いていることが感じられます。
ライブ活動においても、ホールや野外フェスだけでなく、ライブハウスでの公演も行っており、観客との距離が近い空間での演奏を大切にしています。「月へひととびツアー」では、久しぶりのライブハウスでの演奏が話題となり、観客との一体感が強く印象に残るものとなりました。
甲本ヒロトは、ライブの場を「来たい人にとっての天国」と語り、会場の規模や観客数に左右されない自由な表現を貫いています。その姿勢は、バンドの音楽にも反映されており、毎回の作品においても「新しい音楽をやるつもりはない、ロックンロールをやりたいんだ」という信念が貫かれています。
60代を迎えた現在も、甲本ヒロトは変わらぬエネルギーでステージに立ち続けています。歌声やパフォーマンスに衰えはなく、むしろ年齢を重ねたことで生まれる深みが加わり、観る者に強い印象を与えています。ザ・クロマニヨンズは、今もなおロックンロールの鼓動を鳴らし続ける存在として、多くのファンに支持されています。
▶▶ 詳しくはこちらの記事もどうぞ
ブギ連での新たな表現の場
甲本ヒロトは2019年、ギタリスト内田勘太郎とともに「ブギ連」を結成しました。内田は憂歌団のメンバーとして知られ、ブルースに深く根ざした音楽性を持つ人物です。二人の共演は、これまでのバンド活動とは異なるアプローチを生み出し、より濃密で骨太なブルースサウンドが展開されるユニットとなりました。
ブギ連は、同年に1stアルバム『ブギ連』をリリースし、東名阪でライブを開催しました。シンプルな編成ながらも、ステージでは圧倒的な熱量と迫力を放ち、観客を魅了しました。日本語によるストレートなブルースを軸にした楽曲は、これまでの甲本ヒロトの作品群とは一線を画し、音楽的な幅の広さを感じさせるものでした。
その後、しばらく表立った活動はありませんでしたが、2024年に約5年ぶりの再始動が発表されました。10月には2ndアルバム『懲役二秒』をリリースし、東京、名古屋、京都、大阪、福岡を巡るライブツアー「第2回 ブギる心」を開催する予定です。アルバムには「畑の鯛」「痛えで」「49号線のブルース」など、ユニークなタイトルの楽曲が並び、ボーナスディスクも付属する豪華な内容となっています。
ブギ連の音楽は、甲本ヒロトの歌とハーモニカ、内田勘太郎のギターが織りなす濃密なセッションによって構成されており、ライブではその場限りの即興演奏も見どころのひとつです。二人の音楽的な相性の良さが際立ち、観客との距離が近い空間での演奏は、まさに一期一会の体験となっています。
甲本ヒロトはザ・クロマニヨンズとしての活動も継続しながら、ブギ連という別の表現の場を持つことで、音楽への探求心をさらに深めています。ジャンルに縛られず、自由な発想で音楽を楽しむ姿勢は、長年にわたって第一線で活躍してきた彼の根底にあるものです。
歌唱スタイルの変遷と特徴

甲本ヒロトの歌唱スタイルは、バンドの変遷とともに大きく変化してきました。初期のTHE BLUE HEARTS時代には、がなり立てるような荒削りな発声が特徴で、腹の底から絞り出すような低音が響くスタイルでした。ステージ上では激しく動きながらも、声がぶれることなく芯の通った歌声を保ち続ける姿が印象的でした。
しかし、バンドが成熟するにつれて、歌い方にも変化が見られるようになります。特に5枚目のアルバム『HIGH KICKS』以降は、声のトーンが軽やかになり、弾むような歌い方が増えていきました。この変化には、喉への負担を軽減する目的もあったとされ、よりメロディアスで滑らかな表現が可能になりました。
THE HIGH-LOWSでは、ポップな楽曲が増えたこともあり、歌唱にも柔らかさや遊び心が加わりました。フレーズの語尾を崩したり、テンポを意図的にずらしたりすることで、感情やノリを前面に押し出すスタイルが定着していきました。技術的な装飾を避け、あくまでストレートに歌う姿勢は一貫しており、ビブラートやフェードなどの技巧はほとんど使われていません。
現在のザ・クロマニヨンズでは、再び初期の荒々しいスタイルに近づいています。がなりや仮声帯を使ったノイジーな発声が多く、語頭や語尾に独特のノイズを乗せることで、エモーショナルな表現を強調しています。一方で、楽曲によっては繊細なニュアンスを込めた歌い方も見られ、表現の幅は広がっています。
甲本ヒロト自身は、自分の歌い方を「分からない」と語ることがありますが、長年のライブ経験によって体に染みついたスタイルが自然と表れていると考えられます。どんな状況でも安定した声を出せるのは、実戦を重ねてきたからこそ身についた技術であり、彼の歌唱はまさに身体と音楽が一体となった表現と言えます。
ハーモニカやギターなどの楽器へのこだわり
甲本ヒロトはボーカルだけでなく、ギターやハーモニカの演奏にも積極的に取り組んでいます。ライブではハンドマイクで歌う姿が印象的ですが、楽曲によってはギターを抱えたり、ハーモニカを吹いたりと、演奏者としての側面も強く表れています。
ハーモニカに関しては、HOHNER社製の10穴ハーモニカ「Special 20」を長年愛用しています。このモデルはABS樹脂製のボディで、湿気に強く、扱いやすい点が特徴です。ライブではアンプと組み合わせて使用されることが多く、爆音のロックバンドの中でもしっかりと音を届けることができます。口元に金属パーツが出ていないため、激しい演奏でも唇を傷つけにくく、ステージ上での安心感にもつながっています。
また、ブギ連での活動時には「Marine Band Crossover」という竹製ボディのモデルも使用しています。こちらはアンプを使わない場面で活躍し、生音がはっきりと響くため、ブルース色の強い楽曲に適しています。甲本ヒロトはこれらのハーモニカをキーごとに複数本持ち歩き、楽曲に応じて使い分けています。
ギターについては、THE HIGH-LOWS時代にGibsonのフライングVやSG’69、American Showster BIKERなどの個性的なモデルを使用していました。アコースティックギターではMartin HD-35を選び、繊細な表現にも対応しています。ギター演奏は頻度こそ多くありませんが、楽曲の雰囲気に合わせて登場し、ステージに彩りを加えています。
ハーモニカ用のアンプには、世界初のハーモニカ専用真空管アンプ「GUYATONE HP-300A」を使用しており、ライブでは甲本ヒロトの背後に設置されていることが多いです。マイクも同社製の「Harpist-15M」を使い、ハーモニカの音を的確に拾う工夫がされています。
これらの楽器や機材は、甲本ヒロトの音楽性を支える重要な要素です。歌だけでなく、楽器を通じて音の質感やニュアンスを細かく調整し、ライブやレコーディングでの表現力を高めています。道具へのこだわりは、彼の音楽に対する真摯な姿勢を物語っています。
▶▶ ザ・クロマニヨンズのCDなどをアマゾンでチェックしてみる
▶▶ 甲本ヒロトさんに関する本などをアマゾンでチェックしてみる
甲本ヒロトの人物像とエピソードから見る姿勢
岡山から東京へ、音楽への決意

甲本ヒロトは岡山県立岡山操山高等学校を卒業後、法政大学経済学部に進学するために上京しました。高校時代から音楽に強い関心を持っていた彼にとって、東京での生活は音楽活動を本格化させるための大きな一歩でした。大学進学は両親との約束でもあり、音楽を続けるための現実的な選択でもありました。
上京後は、渋谷区幡ヶ谷の四畳半のアパートに住み、家賃は月額14,000円でした。奨学金を得て生活を支えながら、学業と音楽活動を両立させる日々を送っていました。当時の東京は、ライブハウスや音楽スタジオが集まる活気ある街であり、甲本ヒロトにとっては刺激に満ちた環境でした。
大学では経済学を学びながらも、音楽への情熱は冷めることなく、バンド活動にのめり込んでいきました。やがて学業との両立が難しくなり、2年で大学を中退する決断をします。その際には「今日やめないとダメだ」と強く言い切り、音楽の道に進む覚悟を示しました。
この時期には、THE BLUE HEARTSの代表曲「人にやさしく」などもすでに作られており、音楽的な方向性は明確になっていました。プロとしての道筋が整っていたわけではありませんが、「なんとかなる」という前向きな気持ちで活動を続けていました。
甲本ヒロトの東京での生活は、音楽にすべてを捧げる覚悟と、限られた環境の中で自分の表現を磨いていく日々でした。四畳半の部屋から始まった彼の音楽人生は、やがて日本のロックシーンを大きく揺るがす存在へと成長していきます。
シーナ&ザ・ロケッツとの出会い
甲本ヒロトが中学生の頃、強く憧れていたバンドがシーナ&ザ・ロケッツでした。ロックに目覚め始めたばかりの時期に、彼らの存在は大きな刺激となり、ライブに行きたいという思いを抱いていましたが、当時は実際に足を運ぶことができませんでした。
それでも、偶然の巡り合わせが彼に忘れがたい体験をもたらします。岡山でシーナ&ザ・ロケッツがライブを行った後、地元のラジオ局に出演することを知った甲本ヒロトは、ラジオ局の近くで出待ちをしていました。まだロック未経験だった彼は、勇気を出して鮎川誠に声をかけ、「僕にもロックンロールができる気がするんです」と夢を語りました。
その言葉に対して、鮎川誠は「お前、大丈夫!きっとできるよ!」と力強く励ましました。この一言は、甲本ヒロトにとって大きな支えとなり、音楽の道へ進む決意を後押しするものとなりました。憧れの存在から直接言葉をもらった経験は、彼の心に深く刻まれ、後のバンド活動や表現の原動力となっていきます。
この出会いは、単なるファンとアーティストの交流を超えた、未来への扉を開く瞬間でした。甲本ヒロトが後にTHE BLUE HEARTSをはじめとする数々のバンドでロックの歴史を築いていく中で、シーナ&ザ・ロケッツとのこのエピソードは、彼の原点のひとつとして語り継がれています。
▶▶ 詳しくはこちらの記事もどうぞ
学生時代の生活とバイト経験

甲本ヒロトが法政大学に進学して上京した際、住まいとして選んだのは渋谷区幡ヶ谷の四畳半のアパートでした。家賃は月額14,000円で、奨学金を受けながらの生活でした。狭いながらも自分の表現を育てる空間として、音楽活動の拠点となっていました。
大学では経済学を学びつつも、音楽への情熱は日々高まっていきました。そんな中、生活費を支えるために始めたアルバイト先が、下北沢にある老舗中華料理店「珉亭」です。この店は1964年創業で、地元の人々やカルチャー関係者に長く親しまれている場所です。
珉亭では、甲本ヒロトのほかにも俳優の松重豊が同時期に働いており、若者たちが夢を語り合う場としても機能していました。厨房で汗を流しながら、音楽や演劇に打ち込む仲間たちと交流を深める日々は、彼にとってかけがえのない時間だったといえます。
店の名物は、赤いチャーハンとラーメンのセット「ラーチャン」で、ライブ後に立ち寄るミュージシャンも多く、甲本ヒロトもこの店での経験を通じて、音楽と日常が交差する感覚を体験していました。店内には彼のサインも飾られており、当時の記憶が今も残されています。
この時期の生活は、音楽活動とアルバイト、仲間との交流が密接に結びついたものでした。学業を中退して音楽に専念する決断を下すまでの間、幡ヶ谷のアパートと下北沢の珉亭は、甲本ヒロトの青春の舞台として深く刻まれています。
兄・甲本雅裕との関係性
甲本ヒロトには2歳年下の弟、甲本雅裕がいます。兄が音楽の世界で活躍する一方、弟は俳優として映画やドラマに多数出演し、名脇役として知られる存在です。異なる分野で活動している二人ですが、互いの道を尊重し合い、温かな関係を築いています。
甲本雅裕は大学卒業後、アパレル会社に就職しましたが、映画への関心が高まり、役者の道へ進む決意を固めました。上京後は兄が働いていた中華料理店でアルバイトをしながら、劇団に所属して演技を学びました。兄のライブに顔を出すこともあり、音楽と演劇という異なる表現の場で互いに刺激を受け合っていた様子がうかがえます。
甲本ヒロトは、弟の俳優としての挑戦を応援する気持ちを込めて、THE BLUE HEARTSの楽曲「キング・オブ・ルーキー」を制作しました。この曲はアルバム『DUG OUT』に収録されており、短いながらも前向きなエネルギーに満ちた作品です。タイトルには「新人王」という意味が込められており、弟の新たなスタートを祝福するメッセージが込められています。
子ども時代には、兄弟で同じ部屋を使っていたこともあり、時には距離を置きたくなるような時期もあったようですが、裏山で一緒に遊ぶなど、仲の良い兄弟としての思い出も多く残っています。現在では、テレビ番組で弟が兄について語る場面もあり、兄の音楽活動を誇りに思っている様子が伝わってきます。
甲本雅裕が出演する番組を甲本ヒロトが録画して応援しているというエピソードもあり、兄弟の絆は今も変わらず続いています。互いに異なる道を歩みながらも、家族としてのつながりを大切にしている姿勢が、彼らの活動の根底にあるようです。
音楽以外の活動や発言の背景

甲本ヒロトは音楽活動の枠を超えて、さまざまな趣味や関心を持ち続けています。その一つがバイクで、若い頃からモッズスクーターに乗っていた経験を皮切りに、現在まで複数の車種を乗り継いできました。ホンダのモンキーやトライアンフ、ハーレーダビッドソンなど、個性的なバイクを所有しており、楽曲の中にもバイクにまつわる描写が登場します。事故を経験してもなお、バイクへの愛情は変わらず、季節を問わず乗り続けています。
昆虫採集も彼の大切な趣味の一つです。夏になると捕虫網を持って山へ出かけることもあり、虫の生態に対する興味は深く、ラジオ番組などでも専門的な話題を披露することがあります。ムシクソハムシなど、一般には馴染みのない昆虫についても詳しく語ることができ、知識の豊富さがうかがえます。虫に関する楽曲もいくつか存在し、歌詞の中に昆虫の名前や特徴がさりげなく織り込まれています。
アニメへの関心も根強く、特に『タイムボカンシリーズ』を好んでいます。音楽を担当していた山本正之との交流もあり、THE COATS時代には彼の楽曲を演奏したこともあります。その後、甲本ヒロト自身がタイムボカン関連の楽曲でボーカルを務めるなど、アニメと音楽が交差する場面も生まれました。アニメの世界観やキャラクターから受けた影響は、彼の創作にも自然と反映されています。
これらの趣味は、単なる余暇の過ごし方ではなく、甲本ヒロトの表現活動に深く結びついています。バイクの疾走感、昆虫の生命力、アニメのユーモアや冒険心は、彼の歌詞やステージパフォーマンスに色濃く現れており、音楽の背景にある豊かな感性を形づくっています。
病気や怪我からの復帰エピソード
甲本ヒロトはこれまでの音楽活動の中で、病気や怪我による困難を何度も経験していますが、そのたびにステージへ戻り、観客の前に立ち続けてきました。2007年には急性疾患により、予定されていたライブのうち6公演を延期する事態となりました。体調を崩した中でも、無理をせずに回復を優先し、万全の状態で復帰する姿勢は、音楽に対する誠実さを感じさせるものでした。
2017年にはバイクで転倒し、鎖骨と肋骨を骨折するという大きな怪我を負いました。一部のライブは延期されましたが、甲本ヒロトはアームホルダーを装着した状態でステージに立ち、演奏を続けました。激しい動きは控えながらも、歌声には力強さが宿っており、観客との一体感を損なうことはありませんでした。
さらに2025年には、フジロックフェスティバルのステージで松葉杖をついて登場し、骨折を抱えながらもライブを敢行しました。雨で滑りやすくなった野外ステージでの転倒が原因とされており、右足首を骨折した状態での出演でした。椅子を使わずに立ったまま歌い続け、「世の中がどんどん壊れていくのはなんでか分かるか?」という力強い言葉をステージ上で放ち、観客の心を揺さぶりました。
こうしたエピソードからは、甲本ヒロトの音楽に対する強い意志と、観客との約束を守ろうとする責任感が伝わってきます。怪我や病気を乗り越えてステージに立つ姿は、単なるプロ意識を超えた、表現者としての覚悟の表れです。どんな状況でも音楽を届けようとするその姿勢は、多くの人々に勇気と感動を与え続けています。
インタビューで語られる価値観

甲本ヒロトは、インタビューの場で音楽や人生に対する考え方を率直に語ることが多くあります。その言葉には、飾らない誠実さと、表現者としての自然体がにじみ出ています。たとえば「誰にでも出来るからボーカルを選んだ」という発言には、特別な才能や技術よりも、誰もが持つ可能性を信じる姿勢が込められています。
彼は、音楽活動を「成り行き」と表現することがあります。曲作りやバンドの方向性についても、あらかじめ計画するのではなく、その時々の流れに身を任せていると語っています。これは、偶然や直感を大切にするスタイルであり、型にはまらない自由な創作を支える考え方です。
また、「バンド活動は全部が楽しい」と語るように、ライブやツアー、レコーディングといった一つひとつの活動に対して、純粋な喜びを感じていることが伝わってきます。仲間と一緒に音を鳴らすこと、観客と空間を共有することが、彼にとっての音楽の本質であり、日常の延長線上にあるものとして捉えられています。
年齢に対する考え方もユニークです。「30歳になったら何かが変わると思っていたけど、何も変わらなかった」と語り、60歳を迎えた今も「何も変化はない」と言い切っています。年齢や世間の価値観に縛られず、自分のペースで生きることを大切にしている姿勢がうかがえます。
さらに、「受け身でいることが大事」と語る場面もあり、音楽に対して構えすぎず、自然に楽しむことを重視しています。バンドメンバーとの関係性や、日々の活動の中で感じる小さな感動を積み重ねることが、彼の創作の原動力となっています。
甲本ヒロトの言葉には、音楽を特別なものとしてではなく、誰もが触れられる日常の一部として捉える視点があります。その価値観は、彼の歌詞やステージパフォーマンスにも反映されており、多くの人々に共感を呼び続けています。
甲本ヒロトの歩みから見える音楽人生の全体像
- 高校時代にラウンド・アバウトで音楽活動を開始
- THE BLUE HEARTSで社会的な支持を獲得した
- THE HIGH-LOWSではポップとロックを融合させた
- ザ・クロマニヨンズで原点回帰のロックを展開した
- ブギ連ではブルースを軸にした新たな表現を模索した
- 歌唱スタイルはバンドごとに柔軟に変化してきた
- ハーモニカやギターなど楽器選びに強いこだわりがある
- 岡山から東京へ進学し音楽に全力を注いだ学生時代がある
- 下北沢の中華料理店でのバイト経験が活動の支えとなった
- シーナ&ザ・ロケッツとの出会いが音楽の原動力になった
- 俳優の弟甲本雅裕との関係性に家族の絆が見える
- バイクや昆虫採集など趣味が創作に影響を与えている
- 怪我や病気を乗り越えてステージに立ち続けている
- インタビューでは自然体の価値観を率直に語っている
- 甲本ヒロトの音楽人生は一貫して自由な表現を貫いている
▶▶ ザ・クロマニヨンズのCDなどをアマゾンでチェックしてみる
▶▶ 甲本ヒロトさんに関する本などをアマゾンでチェックしてみる
▶▶ こちらの記事もどうぞ



