THE BREAKERSについてもっと知りたいと思ったとき、どこから触れればいいのか迷うことがあります。1978年に結成されたTHE BREAKERSは、原宿や新宿の歩行者天国での演奏を皮切りに、モッズ文化とラブソングを軸にした独自のスタイルで注目を集めました。
THE BREAKERSの音楽は、青春の感情をまっすぐに表現し、ライブでは観客との一体感を生み出す熱量に満ちていました。解散後もその影響は色濃く残り、THE BLUE HEARTSへの楽曲継承など、今も語り継がれる存在です。
彼らの軌跡をたどることで、音楽と文化が交差する瞬間に触れることができます。
【この記事のポイント】
- THE BREAKERSの結成から解散までの流れ
- モッズ文化とファッションへのこだわり
- ライブ中心の活動と未発表曲の存在
- THE BLUE HEARTSへの楽曲継承と影響
▶▶ 真島昌利さんのCDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
THE BREAKERSの結成とメンバー構成
真島昌利と杉浦光治による初期トリオ編成
THE BREAKERSは1978年、真島昌利と杉浦光治を中心に結成されたロックバンドです。真島がギターとボーカル、杉浦がベースとボーカルを担当し、ドラムには当時の仲間が加わる形でトリオ編成が組まれました。彼らは高校時代から音楽活動を始めており、バンド名は真島が住んでいた団地で頻繁にブレーカーが落ちていたことに由来しています。
活動初期は、原宿や新宿の歩行者天国での路上ライブが中心でした。週末になると、若者たちが集まるその場所で、彼らはアンプと楽器を持ち込み、即興的に演奏を始めていました。通行人が足を止め、自然と人だかりができるほどの熱気があり、当時の東京のストリートカルチャーの象徴的存在となっていきます。
演奏スタイルは、ラブソングを中心にしたメロディアスな構成で、ビートルズやザ・ジャムなどの英国ロックに影響を受けたサウンドが特徴でした。モッズ文化への関心も強く、ファッションや立ち振る舞いにもこだわりを見せていました。三つボタンのスーツやサイドゴアブーツなど、英国スタイルを意識した装いは、音楽とともに彼らの個性を際立たせる要素となっていました。
この時期のTHE BREAKERSは、まだ音源のリリースには至っていませんでしたが、ライブ活動を通じて着実にファンを増やしていきました。ステージでの一体感や、観客との距離の近さが魅力となり、後のモッズムーブメントの中核を担う存在へと成長していきます。
彼らの音楽は、のちに真島がTHE BLUE HEARTSで発表する楽曲の原型にもなっており、初期の創作活動が後の日本ロックシーンに与えた影響は小さくありません。THE BREAKERSのトリオ時代は、自由で熱量の高い音楽表現が息づいていた貴重な時期でした。
篠原太郎と大槻敏彦の加入による安定期

THE BREAKERSが音楽的に成熟し始めたのは、1981年に篠原太郎と大槻敏彦が正式に加入した時期からです。篠原はギターとボーカルを担当し、大槻はドラムとボーカルを兼任する形で参加しました。これにより、真島昌利(ギター・ボーカル)、杉浦光治(ベース・ボーカル)を含めた4人編成が確立され、バンドとしてのバランスが大きく向上しました。
この編成は、演奏面でも表現力の幅を広げることにつながり、ライブ活動が一気に本格化します。新宿JAM STUDIOや原宿の歩行者天国など、東京のライブシーンを中心に精力的なステージを重ね、観客との一体感を生み出す演奏スタイルが定着していきました。モッズ文化の影響を受けたファッションや振る舞いも、バンドの個性として強く打ち出されていました。
篠原はもともとベース志望でしたが、バンド内での役割調整によりギターを担当することになり、真島とのツインギター体制が生まれました。一方、大槻は中学時代から真島と交流があり、旧知の仲として自然な形でバンドに溶け込んでいきます。彼のドラムは安定感があり、バンドのリズムを支える要として機能しました。
この時期のTHE BREAKERSは、演奏技術だけでなく、楽曲の完成度も高まり、オリジナル曲の制作にも力を入れていました。ラブソングを中心にしたメロディアスな楽曲は、観客の心に響くものが多く、ライブでは定番曲として親しまれていました。後にTHE BLUE HEARTSで発表される楽曲の原型も、この時期に生まれたものが多く含まれています。
4人編成の安定期は、THE BREAKERSにとって最も充実した創作期間であり、バンドとしての方向性が明確になった時期でもあります。メンバーそれぞれが個性を発揮しながらも、ひとつの音楽的な世界観を共有していたことが、当時のライブの熱気やファンの支持につながっていました。
サポートメンバーの参加とライブ体制
THE BREAKERSのライブ活動は、メインメンバーによる演奏に加え、サポートメンバーの参加によってさらに厚みを増していきました。特に後期には、キーボードやサックス奏者が加わることで、音楽の表現力が広がり、ステージの完成度が高まっていきます。キーボード担当としては八木橋カンペーが知られており、彼の演奏はバンドのサウンドに柔らかさと奥行きを加えていました。
サポートギタリストとしては石井アキラが参加しており、杉浦光治の脱退後にはライブの要として活躍しました。彼らの存在は、単なる補助ではなく、バンドの音楽性を支える重要な役割を果たしていました。演奏の幅が広がることで、観客に届ける音の世界もより豊かになり、ライブの魅力が一層深まっていきます。
ステージでは、演奏だけでなくファッションや振る舞いにも強いこだわりがありました。モッズ文化を背景にしたスタイルは、細身のスーツやロンドン調のヘアスタイルなど、視覚的にも印象的で、観客の目を引く要素となっていました。演奏中の立ち振る舞いや表情、楽器の扱い方に至るまで、すべてが一つのパフォーマンスとして統一されており、ライブは音楽と演出が融合した空間として成立していました。
ライブハウスだけでなく、原宿や新宿の歩行者天国、代々木公園などの屋外イベントでも演奏を行い、観客との距離が近いステージを大切にしていました。その場の空気を読みながら即興的に演奏を展開する柔軟さも、THE BREAKERSのライブ体制の魅力のひとつです。
サポートメンバーの参加は、バンドの音楽的な挑戦を支える存在であり、彼らの演奏があったからこそ、THE BREAKERSはライブバンドとしての評価を高めることができました。音楽と演出の両面で観客を魅了するその姿勢は、今も語り継がれるライブ文化の一端を担っています。
メンバー脱退による編成の変化
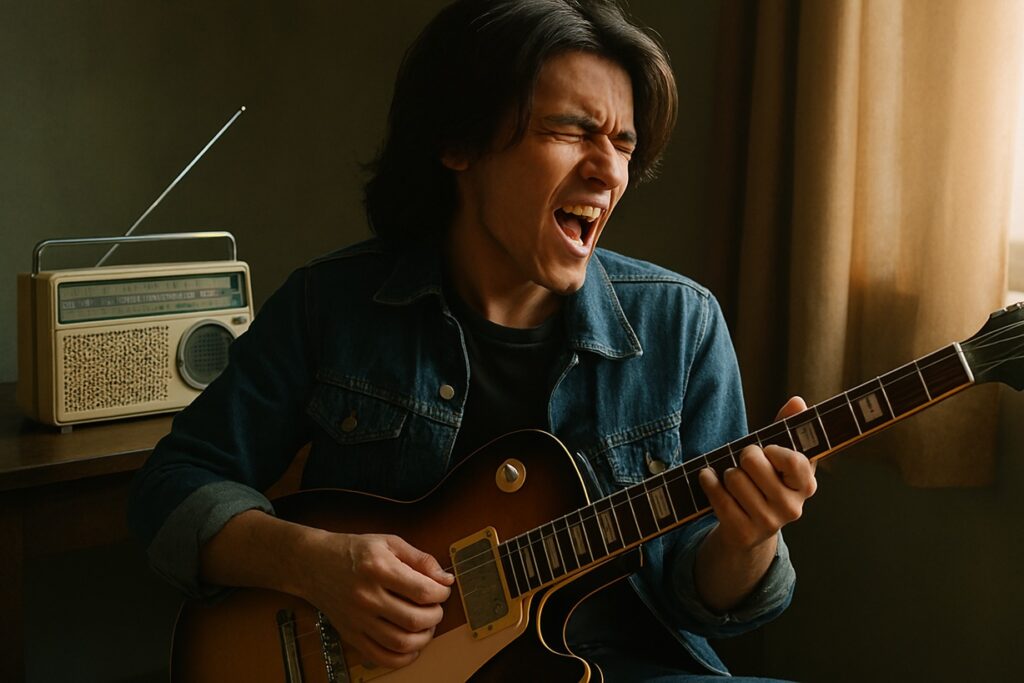
1984年2月、THE BREAKERSの結成メンバーでありリードギターとボーカルを担当していた杉浦光治が脱退しました。彼はバンドの初期から中心的な存在であり、真島昌利とのコンビネーションは音楽面でもステージ面でも重要な役割を果たしていました。杉浦の脱退は、バンドにとって大きな転機となります。
この出来事を機に、バンドは真島昌利、篠原太郎、大槻敏彦の3人編成へと移行します。人数が減ったことで演奏の構成にも変化が生じ、音の厚みや表現の幅を補うためにサポートメンバーの参加が増えていきました。ギターの石井アキラやキーボードの八木橋カンペーなどが加わり、ライブでは多彩なサウンドが展開されるようになります。
音楽性にも揺らぎが見られ、これまでのラブソング中心のメロディアスなスタイルから、より荒削りでストレートなロック色が強まっていきました。メンバーそれぞれがボーカルを担当するスタイルは継続され、個性の異なる歌声が交差することで、バンドの魅力は保たれていました。
活動の中心はライブに移り、音源制作よりもステージでの表現に重きを置くようになります。新宿JAM STUDIOなどのライブハウスでは、熱気ある演奏が繰り広げられ、観客との距離が近い空間での一体感が生まれていました。杉浦の不在を感じさせないほど、残ったメンバーはそれぞれの役割を果たし、バンドとしての存在感を維持していました。
この時期のTHE BREAKERSは、音楽的な試行錯誤とともに、バンドとしての方向性を模索していた時期でもあります。解散までの約1年間、彼らはステージを通じて自分たちの音楽を届け続け、最後まで情熱を失うことなく活動を続けました。
最終期の3人編成と活動スタイル
THE BREAKERSは1984年に杉浦光治が脱退した後、真島昌利、篠原太郎、大槻敏彦の3人編成で活動を継続しました。この最終期は、バンドとしての方向性がより明確になった時期であり、音源制作よりもライブパフォーマンスに重きを置いたスタイルが定着していきます。
演奏の場は主に新宿JAM STUDIOなどのライブハウスで、観客との距離が近い空間での熱量あるステージが特徴でした。3人それぞれがボーカルを担当し、曲ごとに異なる個性が表れる構成は、観る者に飽きさせない魅力を持っていました。ギターとキーボードのサポートメンバーを加えることで、音の厚みを補いながら、表現の幅を広げていました。
この時期の楽曲は、ラブソングを中心にしながらも、よりストレートで荒々しいロックの要素が強まり、ライブでの演奏に最適化された構成が多く見られます。観客の反応をダイレクトに受け止めながら、即興的なアレンジを加える柔軟さもあり、ステージは常に生きた空間として機能していました。
ファッションや振る舞いにも一貫した美学があり、モッズ文化を背景にした三つボタンのスーツやサイドゴアブーツなどのスタイルは、音楽と視覚の両面で観客を魅了しました。演奏中の動きや表情も含めて、ライブはひとつの作品として完成されていた印象があります。
1985年1月25日、新宿JAM STUDIOで開催された「マーチ・オブ・ザ・モッズ」が、THE BREAKERSとしての最後のステージとなりました。このライブには甲本ヒロトが飛び入り参加し、会場は熱狂に包まれました。解散の瞬間まで、彼らは全力で音楽を届け続け、観客の記憶に深く刻まれる存在となりました。
最終期の活動は、音楽に対する純粋な情熱と、ライブという場を通じて人とつながる力を示すものであり、THE BREAKERSの本質が最も鮮明に表れていた時期といえます。
解散後のメンバーの音楽活動

THE BREAKERSが1985年に解散した後、メンバーたちはそれぞれの音楽的な道を歩み始めました。真島昌利は、甲本ヒロトとともにTHE BLUE HEARTSを結成し、日本のロックシーンに大きな足跡を残す存在となります。THE BREAKERS時代に演奏されていた楽曲の一部は、THE BLUE HEARTSやその後のTHE HIGH-LOWS、ザ・クロマニヨンズでも形を変えて発表されており、初期の創作活動が後の代表曲の土台となっています。
篠原太郎は1988年にソロシンガーとしてメジャーデビューを果たし、2枚のアルバムを発表します。その後、ソロ活動に疑問を感じるようになり、1991年には大槻敏彦や古川英俊とともにTHE BRICK’S TONEを結成。バンド活動を再開し、ライブを中心に精力的な活動を続けています。篠原はさらに「ピノキオズ」など複数のユニットにも参加し、ジャンルを越えた音楽表現に挑戦しています。
大槻敏彦はTHE BRICK’S TONEのほか、ピアノトリオなどのユニットでも活動を展開し、ドラム教室の講師としても音楽教育に携わっています。演奏者としてだけでなく、指導者としても音楽に関わり続けており、後進の育成にも力を注いでいます。
解散後も、篠原や大槻は真島のソロツアーやアルバム制作に参加するなど、メンバー同士の交流は続いています。THE BREAKERSで培った音楽的な感性や人間関係は、それぞれの活動の中で生き続けており、バンドの記憶は形を変えて今も音楽の中に息づいています。
THE BLUE HEARTSへ続く楽曲
THE BREAKERSの活動期に生まれた楽曲の一部は、後にTHE BLUE HEARTSで再構成され、正式な作品として発表されています。その代表的な例が「終わらない歌」です。この曲は、THE BLUE HEARTSのファーストアルバムに収録されており、バンドの初期衝動を象徴する楽曲として広く知られています。
「終わらない歌」は、真島昌利がTHE BREAKERS時代に書き始めた楽曲で、当時のライブでも演奏されていた記録が残っています。歌詞には社会への違和感や怒り、そしてそれを乗り越えようとする意志が込められており、ストレートな言葉とシンプルなコード進行が特徴です。この構成は、THE BREAKERSが路上ライブで培った即興性や観客との一体感を反映しているとも言えます。
THE BLUE HEARTSとして再構成された際には、より攻撃的で力強い表現が加わり、放送禁止用語を含むことで話題にもなりました。それでもなお、楽曲が持つメッセージ性は多くの人々の心に響き、時代を超えて支持され続けています。このような継承は、単なる再利用ではなく、音楽的な思想や感情の連続性を示すものです。
THE BREAKERSでの創作活動が、THE BLUE HEARTSの核となる部分に深く関わっていたことは、真島昌利の作詞・作曲スタイルにも表れています。彼が抱えていた社会への疑問や個人の葛藤は、バンドが変わっても一貫して表現され続けており、それが多くの人に共感を与える理由となっています。
「終わらない歌」は、THE BREAKERSの時代から続く“歌い続けること”への信念が形になった楽曲であり、真島の音楽人生を貫くテーマの象徴でもあります。
▶▶ 真島昌利さんのCDなどの作品をアマゾンでチェックしてみる
THE BREAKERSの音楽性とライブ文化
モッズ文化との深い関わりとファッション性

THE BREAKERSは、音楽だけでなくファッションやライフスタイルにおいてもモッズ文化の影響を色濃く受けていたバンドです。モッズとは、1960年代の英国ロンドンで生まれた若者文化で、細身の三つボタンのスーツやバタンダウンシャツ、ミリタリーパーカー(M-51)、そして多数のミラーを装飾したスクーターなどが象徴的なスタイルとされています。
THE BREAKERSのメンバーは、こうした英国モッズの美学を日本のストリートカルチャーに取り入れ、原宿や新宿の歩行者天国でのライブ活動を通じてそのスタイルを体現していました。彼らの衣装は、チャコールグレーやブラックのスーツだけでなく、ピンクやパウダーブルーなどの鮮やかな色合いも取り入れられ、視覚的にも強い印象を残していました。
ファッションは単なる衣装ではなく、音楽と一体となった表現手段として機能していました。ステージ上では、ローファーやモンキーブーツを履き、シャープなサングラスやポークパイハットを合わせることで、観客に強い個性と統一感を伝えていました。こうしたスタイルは、当時の東京の若者たちにとって新鮮で刺激的なものであり、モッズ文化の再解釈として受け入れられていきました。
THE BREAKERSのファッション性は、音楽のジャンルや演奏スタイルと密接に結びついており、彼らのライブは音とビジュアルが融合した空間として成立していました。モッズ文化の精神を受け継ぎながらも、日本独自の感性を加えたそのスタイルは、後のモッズ系バンドやサブカルチャーにも影響を与える存在となりました。
原宿・新宿の歩行者天国での演奏活動
THE BREAKERSが結成された1978年当初、彼らの主な活動の場は原宿や新宿の歩行者天国でした。週末になると、若者たちが集まるその空間は、音楽やファッション、ダンスなどが入り混じる自由な表現の場となっており、バンドにとっては観客と直接つながる貴重なステージでした。
彼らはアンプやラジカセを車のバッテリーにつないで電源を確保し、即興的に演奏を始めていました。通行人が足を止め、自然と人だかりができるほどの熱気があり、演奏はその場の空気を巻き込むような勢いを持っていました。ラブソングを中心としたメロディアスな楽曲は、耳に残りやすく、初めて聴く人にも親しみやすいものでした。
当時の原宿ホコ天は、竹の子族やローラー族などの若者文化が交差する場所でもあり、THE BREAKERSの演奏はそのカルチャーの一部として受け入れられていました。彼らのファッションもモッズスタイルを基調としており、細身のスーツやロンドン調のヘアスタイルが、音楽とともに視覚的なインパクトを与えていました。
新宿では、歩行者天国だけでなくライブハウスでも活動を広げていきましたが、路上での演奏は彼らの原点とも言える存在でした。観客との距離が近く、反応を肌で感じながら演奏することで、バンドとしての一体感や表現力が磨かれていきました。
この時期のTHE BREAKERSは、音源のリリースこそなかったものの、ライブを通じて着実にファンを増やし、後のバンドブームの土壌を作る一翼を担っていました。歩行者天国での演奏活動は、彼らの音楽が街とともに生きていた証であり、当時の東京の若者文化を象徴する風景のひとつです。
ラブソング中心のメロディアスな楽曲構成

THE BREAKERSの音楽は、ラブソングを軸にしたメロディアスな構成が特徴です。彼らの楽曲には、恋愛の喜びや切なさ、青春の葛藤といった感情が繊細に描かれており、聴く人の心に自然と染み込むような魅力があります。アップテンポでありながら、どこか優しさを感じさせるメロディラインは、当時の若者たちの感性に深く響いていました。
歌詞には、日常の中でふと感じる孤独や希望、誰かを思う気持ちが込められており、派手な演出よりも言葉の力で感情を伝えるスタイルが印象的です。メンバーそれぞれがボーカルを担当することで、曲ごとに異なる視点や感情が表現され、バンドとしての多様性を生み出していました。
演奏スタイルは、60年代のブリティッシュ・ビートをベースにしながらも、日本的な情緒を感じさせるアレンジが施されており、モッズ文化との親和性も高いものでした。ギターのカッティングやベースライン、ドラムのリズムが一体となって、シンプルながらも奥行きのあるサウンドを作り上げていました。
THE BREAKERSは、メッセージ性の強い社会派の楽曲ではなく、あえてラブソングを中心に据えることで、聴く人の個人的な感情に寄り添う音楽を届けていました。その姿勢は、パンクスピリットを内包しながらも、優しさとカッコ良さが共存する独自の世界観を築いていたと言えます。
彼らが残したオリジナル曲は百曲以上にのぼるとされており、その多くが未発表ながらも、ライブで披露されたことでファンの記憶に刻まれています。THE BREAKERSのラブソングは、時代を超えて共感を呼ぶ力を持ち、今もなお語り継がれる存在となっています。
パンクスピリットを内包したステージング
THE BREAKERSのライブは、パンクスピリットを内包したエネルギッシュなステージングが大きな魅力でした。演奏スタイルは、ブリティッシュ・ビートを基盤にしながらも、荒々しくストレートな表現が際立っており、観客との距離を感じさせない一体感が生まれていました。彼らは、音楽だけでなくステージ上での動きや表情、振る舞いにまでこだわり、ライブという空間を全身で表現していました。
特に印象的なのは、メンバー全員がボーカルを担当し、曲ごとに異なる個性を発揮していた点です。真島昌利の叫ぶような歌声、篠原太郎の柔らかくも力強いボーカル、大槻敏彦のリズムを支えるドラムと歌の融合が、ステージに厚みと躍動感をもたらしていました。演奏中は、足を踏み鳴らしながらストンピングする姿や、観客に向かって身を乗り出すような動きが見られ、まるでステージ全体が生き物のように躍動していました。
彼らのステージングは、単なる演奏ではなく、観客と感情を共有する場として機能していました。ライブハウスでは、観客が拳を突き上げて応える場面も多く、コール&レスポンスが自然に生まれるほどの熱気がありました。その場の空気を読みながら即興的に演奏を展開する柔軟さもあり、毎回のライブが異なる表情を見せていました。
パンクの精神は、反骨や自由だけでなく、自己表現への強い意志としてTHE BREAKERSのステージに息づいていました。彼らは、メッセージソングではなくラブソングを選びながらも、演奏の熱量で社会への問いかけや若者の感情を代弁していたとも言えます。その姿勢は、観客にとっても共鳴しやすく、ライブは単なる音楽イベントではなく、心を揺さぶる体験の場となっていました。
解散ライブ「マーチ・オブ・ザ・モッズ」では、涙を流しながら最後まで叫び続ける姿が印象的で、彼らのステージングがどれほど真摯で情熱的だったかを物語っています。喉が引き裂かれるまで歌い続けるその姿は、まさにパンクスピリットの体現であり、観客の記憶に深く刻まれる瞬間となりました。
未発表曲が後の名曲の原型となった背景

THE BREAKERSの活動期には、正式な音源リリースに至らなかった未発表曲が数多く存在していました。その中には、後にTHE BLUE HEARTSで発表された楽曲の原型となるものも含まれており、バンドの音楽的な継承を示す重要な手がかりとなっています。
代表的な例として挙げられるのが「終わらない歌」です。この曲はTHE BLUE HEARTSのファーストアルバムに収録され、バンドの象徴的な存在として知られていますが、原型はTHE BREAKERS時代にすでに演奏されていました。当時のライブでは、まだ完成されていないラフな形で披露されていたものの、歌詞やメロディの核となる部分はすでに存在しており、真島昌利の創作スタイルが色濃く反映されていました。
THE BREAKERSでは、ラブソングを中心にしながらも、若者の感情や社会への違和感を描いた楽曲が多く作られていました。その中には、後にTHE BLUE HEARTSで再構成されることになる「少年の詩」や「未来は僕らの手の中」といった楽曲の原型とされるものもあり、ライブ音源やファンの記憶を通じてその存在が確認されています。
未発表曲が名曲へと昇華していく過程には、バンドの解散と再編成という転機が大きく関わっています。THE BREAKERSで培われた演奏スタイルや歌詞の世界観は、THE BLUE HEARTSの活動に受け継がれ、より洗練された形で世に出ることになりました。この流れは、単なる再利用ではなく、音楽的な思想や感情の連続性を示すものであり、真島昌利の創作における一貫したテーマ性がそこに見て取れます。
THE BREAKERSの未発表曲は、公式な音源として残されていないものの、ライブ映像やファンの記録を通じて今も語り継がれています。それらの楽曲が後の名曲の土台となったことは、バンドの存在が一時的なものではなく、長く音楽の中に生き続けている証でもあります。
ファーストシングルの幻と自主制作の試み
THE BREAKERSは1983年、メジャーデビューに向けてファーストシングルの制作を進めていました。予定されていた楽曲は「涙のCOOL DANCING」と「ダイヤルを廻すだけでいいのに」の2曲で、すでに業界向けのサンプルカセットが出回るほど、リリースは目前まで進んでいました。しかし、所属事務所とレコード会社との間で初回プレス数に関する意見が折り合わず、発売は白紙となってしまいます。
この出来事は、バンドにとって大きな転機となりました。商業的な流通には乗らなかったものの、メンバーたちは音源を残すことへの強い意志を持ち続けており、翌1984年には自主制作によるリリースの話も浮上します。実際に録音やジャケット制作の準備が進められていた記録もあり、ファンの間では「幻のシングル」として語り継がれる存在となっています。
自主制作の試みは、音楽に対する情熱と、表現を止めないという姿勢の象徴でもありました。当時のライブでは、これらの楽曲が頻繁に演奏されており、観客の記憶の中で生き続けています。特に「涙のCOOL DANCING」は、真島昌利のソロ作品や後のバンド活動にも影響を与えた楽曲として知られ、THE BREAKERSの音楽的な核を感じさせる一曲です。
結果的に、正式な音源として世に出ることはありませんでしたが、制作過程そのものがバンドの創作意欲を物語っています。彼らが音楽に込めた思いは、形にならなくても人々の心に届いており、未発表であっても価値ある作品として受け止められています。
この幻のシングルは、THE BREAKERSというバンドがどれほど真摯に音楽と向き合っていたかを示すエピソードであり、彼らの活動が単なる青春の記録ではなく、音楽史の一部として刻まれていることを証明しています。
解散ライブ「マーチ・オブ・ザ・モッズ」の熱狂

1985年1月25日、新宿JAM STUDIOで開催された「マーチ・オブ・ザ・モッズ」は、THE BREAKERSにとって最後のステージとなりました。このイベントは、モッズ文化をテーマにしたライブイベントであり、彼らの音楽とスタイルが最も鮮やかに表現された一夜でした。会場には、モッズファッションに身を包んだ若者たちが集まり、虹色の瞳を持つ少年少女たちがステージを見つめる中、バンドは全力の演奏を披露しました。
この日のライブには、甲本ヒロトが飛び入り参加する場面もあり、観客の熱気は最高潮に達しました。真島昌利、篠原太郎、大槻敏彦の3人は、涙を流しながら最後まで歌い続け、喉が引き裂かれるほどの叫びでステージを締めくくりました。その姿は、音楽にすべてを捧げた者たちの覚悟と情熱を感じさせるもので、観客の記憶に深く刻まれる瞬間となりました。
演奏された楽曲は、ラブソングを中心に、青春の痛みや希望を描いたものが多く、観客との一体感を生む構成でした。モッズ文化の象徴である三つボタンのスーツやサイドゴアブーツを身にまとい、彼らは音楽とファッションの融合を体現していました。ステージ上では、ストンピングや即興的な演奏が繰り広げられ、ライブはまさに生きた表現の場となっていました。
この解散ライブは、THE BREAKERSの集大成であると同時に、東京モッズシーンの象徴的な出来事でもありました。彼らの持つアティチュードは、単なるスタイルではなく、時代を生きる若者たちの感情そのものを映し出していたと言えます。「マーチ・オブ・ザ・モッズ」は、音楽と文化が交差する熱狂の夜として、今も語り継がれています。
THE BREAKERSの軌跡から見える音楽と文化の継承
- THE BREAKERSは1978年に真島昌利らが結成した
- 初期は原宿や新宿の歩行者天国で活動した
- モッズ文化を背景にしたファッションが特徴的だった
- ラブソング中心のメロディアスな楽曲構成が魅力だった
- パンクスピリットを内包したライブ演出が印象的だった
- サポートメンバーの参加で演奏の幅が広がった
- 杉浦光治の脱退後は3人編成で活動を継続した
- 最終期はライブハウス中心の活動スタイルに移行した
- 自主制作による音源づくりが試みられていた
- 幻のファーストシングルはファンの記憶に残る存在
- 未発表曲が後の名曲の原型となっていた
- THE BLUE HEARTSで楽曲が再構成されて発表された
- 解散ライブ「マーチ・オブ・ザ・モッズ」は熱狂の一夜だった
- 解散後もメンバーはそれぞれ音楽活動を継続している
- THE BREAKERSの精神は今も音楽の中に息づいている

